4月15日(火) わからないことに意味がある
宗門の仕事の関係で、森達也さん(映画監督・ドキュメンタリー作家)と語り合う機会を得た。
森さんとは何回か会っているが、会うたびに森さんの生きる姿勢に教えられる。森さんは死刑の問題をめぐって3年以上にわたって様々な取材を続けながら、死刑の本質を直視し続け、その記録である『死刑』(朝日出版社)を1月に出版した。
 森達也さん
森達也さん
 学ぶことが多かったです
学ぶことが多かったです
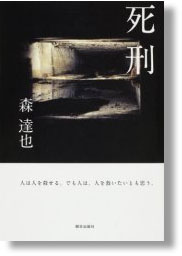
『死刑』(朝日出版社)。本体1,600円+税
森さんが死刑に関心を持つようになったのは、オウム真理教の地下鉄サリン事件以降に形成された社会状況や人間の姿にあった。オウム事件を追い、ドキュメンタリー映画『A』と『A2』を製作した森さんは、死刑を宣告されたオウム信者と会うことを通して死刑に疑問を持つようになる。森さんによれば、オウムパニックの原因は「動機の不確かさ」にあった。なぜオウムがサリンを撒いたのか、その動機がわからないことが大きな不安を作り上げ、異常なまでのセキュリティー社会になった。オウム事件以降、いわゆる「善」「悪」二元論が突出してしまい、悪を徹底的に攻撃し、異物を排除する社会状況が作られ、それがメディアを通して強固になっていった。
死刑存置を求める人が実に8割を超えるのは、この状況から生まれたものだ。世界的な流れでは死刑は廃止に向かっているが、日本は実際に年々犯罪が減っているにもかかわらず、死刑判決が増加しているのは明らかに矛盾である。つまり、死刑について考えることが奪われた社会になってしまったということであろうか。まさしく思考停止である。森さんの言葉で言えば、死刑が不可視の領域に位置しているということだ。
被害者遺族への救済や社会保障がこれまで軽視されてきたことは事実で、それを変えていかねばならないが、それと死刑を同一に論じるべきではないし、殺人等を犯した者は、国家によって殺されてもいいということにはならないと森さんは言う。死刑というが殺刑が正しい。森さんは、国家が主権を持つ国民を殺すことに正当性はまったくなく、死刑を存置する理由のほとんどは論破されていることを、取材を通して確信する。どんな人間でも、生きる価値、いのちに優劣はない。決して殺してはならない。
ところが死刑は人間存在そのものをすべて否定し、人間の可能性を断ち切ってしまうのだ。死刑存置が論理の上では破綻していても、死刑存置を求める心情の根底には不安や恐怖がある。そういう情緒の問題に死刑の本質があるはずだと森さんは追求する。
そのようななかで、被害者、加害者双方を知ることの大切さを森さんは力説する。自分が出会った人がやがて殺されるかもしれないということを絶対に肯定できないと言う。これは論理でもないし、情緒でもなく、敢えて言葉にすれば「本能」に近いと森さんは表現している。「人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う」という森さんの言葉に、人間の深い悲しみと、人間への深い信頼を感じる。森さんは人間が好きなのだとつくづく思った。
『死刑』は、死刑廃止の立場を取りつつも、どこかに曖昧な気持ちがあることもけっしてごまかさないで素直に語られている。森さん自身が死刑の問題に自分なりの答えを求めて苦悩し、また死刑問題を縁として、生きることの意味、人間とは何かを希求しているところに大きな価値がある。森さんは、死刑廃止の側だけでなく、死刑存置の人たちにも会って取材し、双方の考えや具体的問題に学び、死刑の本質を探ろうとした点に森さんの姿勢のすばらしさがあると思う。自分が正しいという眼を見る眼を持っているとでもいおうか、わからなさ、曖昧さというところに実は大切な意味があることを教えてくれている。それこそが善悪といった二元論に陥らない生き方というか、陥ったとしてもそれに気づいていくことが大切だというところまで語っているように読み取れた。
『死刑』は死刑を考える上で様々な視座を与えてくれるだけでなく、取材を続けながら悶々とする森さんの姿、その姿に自分自身を発見することができる好著である。死刑の問題を縁として、人間を明らかにしていくところに、他の死刑関係書物とちがった特色がある。多くの人々に読んでもらいたいと思う。
〔2008年4月18日公開〕
