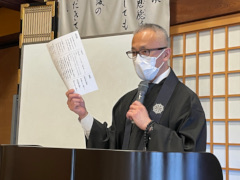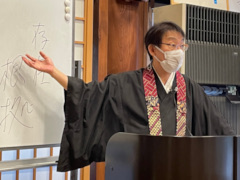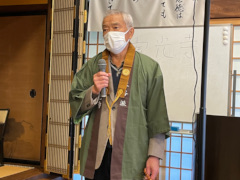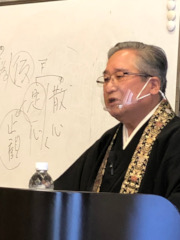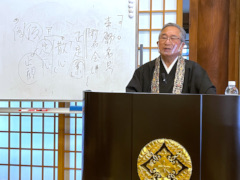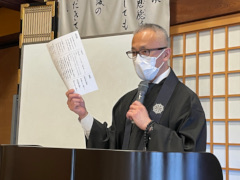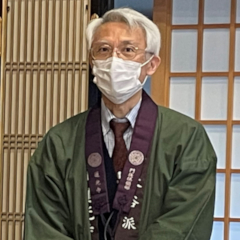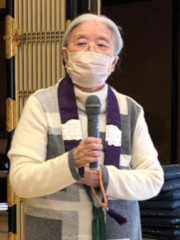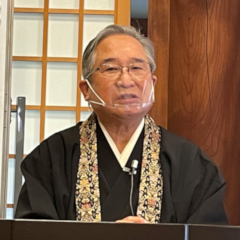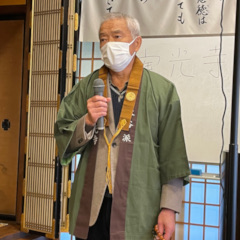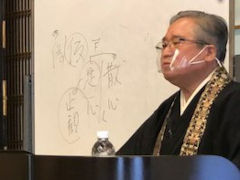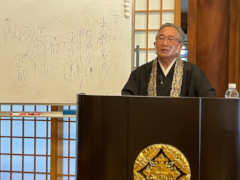報恩講のお知らせ
2022年10月10日公開
報恩講清掃奉仕
「報恩講」は全てのご門徒によって勤められる法要です。報恩の心をもって清掃して、本堂をピカピカにして「報恩講」をお迎えしましょう。ご参加できるご門徒はお寺までご連絡ください。
報恩講
法要の概要
コロナ下のため、従来のお勤めをいたしますと長時間になるため、残念ではありますが、「大逮夜法要」「晨朝法要」「結願日中法要」(ご満座)、すべて「正信偈・同朋奉讃」「御文」とさせていただきます。
「大逮夜法要」は、2時から厳修いたします。時間のおまちがえのないようにお願いいたします。
「報恩講の夕べ」は、やなせななさんのお話と歌が披露されますが、感染状況により、歌をビデオで観ていただくこともございますこと、ご了承ください。
「結願日中法要」(ご満座)後の手作り精進料理は中止とし、お持ち帰りのお弁当をご用意いたします。
参詣について
本堂での参詣は、申し込み先着順とさせていただきます。
「大逮夜法要」と「日中法要」(ご満座)はZoom(ズーム)配信いたします。ご希望の方は、
CBE07907@nifty.com
にメールください。URL等を送信いたします。
Zoom(ズーム)で視聴いただくご門徒は、ご懇志(1法要 1,000円以上)をお送りいただければ幸甚です。
講師紹介
11月5日(土)
大逮夜法要
法話: 「生きることへの意味づけ・価値づけからの解放 ─かけがえのない存在の回復─」(蓮光寺住職)
報恩講の夕べ
「お話と歌」(やなせななさん 奈良県・浄土真宗本願寺派教恩寺住職、シンガーソングライター)
【やなせななさん】
11月6日(日)
日中法要〈御満座〉
法話: 「人の執心、自力の心」(林憲淳先生 岐阜県不破郡・寶光寺住職 81歳)
【林憲淳先生】
報恩講「清掃奉仕」を実施
2022年11月1日公開
10月29日(土)、報恩講に向けて「清掃奉仕」を実施し、22名のご門徒が参加されました。初参加のご門徒もおられ、皆さんから歓迎を受けていました。
このところ昼間も寒さを感じるようになりましたが、この日は23℃の暖かさで、絶好の「清掃奉仕」となりました。
去年は五色幕を新調しました。今年は「報恩講の夕べ」が3年ぶりに開催されます。人数制限での報恩講であっても、少しずつ、従来の報恩講の活気が戻ってくるような、そんな予感を感じながらの清掃奉仕でした。来年は手作り精進料理が復活し、人数制限のない報恩講が勤まることを念じてやみません。
蓮光寺報恩講は11月5日(土)~6日(日)に厳修されます。
2時間の清掃奉仕が終わり、茶話会に入ります。すこしなごんでからみな本堂へ。住職の短めのお話とお参りをして解散。本堂の写真を取り忘れました (涙)
報恩講を厳修
2022年11月11日公開
真宗門徒にとって一番大切な法要である「報恩講」(親鸞聖人のご法事)が11月5日(土)~6日(日)の一昼夜にわたって厳修されました。親鸞聖人のご法事を報恩講と言いますが、ご門徒のご法事も報恩講に相違ありません。どこまでも親鸞聖人を偲びながら(ご門徒の法事の場合は、亡き人を偲びながら)、親鸞聖人が明らかにされた阿弥陀さんの教えを聴聞し、教えを通して迷い深い私のあり方を見つめ直すことが真宗仏事の要です。
今年の報恩講は、3年ぶりに「報恩講の夕べ」が復活し(約40名参加)、大逮夜法要、結願日中は、人数制限を多少オーバーし50名以上の参詣者で、余間にも門徒さんに座っていただきました。もちろんそれに応じた感染対策も徹底いたしました。また、参詣されたご門徒は報恩講の大切さをしみじみ感じられたと思います。来年は人数制限することなく、また手作り精進料理の復活を願ってやみません。
お勤めはすべて「正信偈・同朋奉讃」の同朋唱和とし、大逮夜と晨朝は「御文」、結願日中は「御俗姓御文」の拝読がありました。
「大逮夜法要」は、蓮光寺住職が「生きることへの意味づけ・価値づけからの解放 ―かけがえのない存在むの回復―」をテーマに法話。
「報恩講の夕べ」では3年ぶりに願いが叶い、やなせななさん(奈良県 浄土真宗本願寺派教音寺住職 シンガーソングライター)が「悲しみの先に開かれる世界」をテーマにお話しと歌を披露してくださいました。
「晨朝法要」は、逆にコロナ下なので、朝はちょっとという人が増えたのか少数でしたが、静かな朝の勤行と蓮光寺衆徒櫻橋淳さん(法名:釋淳心)、本多房子前坊守(法名:釋尼芳翠)が感話をされました。
「結願日中法要」(ご満座)では、林憲淳先生(岐阜県不破郡 寶光寺住職)が「人の執心、自力の心」をテーマに熱い法話をしていただきました。
最後の「御礼言上」で広島県庄原市よりオンラインで、蓮光寺門徒を代表して河村和也総代(県立広島大学教授、法名:釋和誠)がご挨拶をしてくださいました。
報恩講はやはり独特の法要です。心地よい疲れを感じています。報恩講の様子を写真でご案内しながら、最後に御礼言上を掲載いたします。法話等はまた後日掲載いたします。
御礼言上 2022
2022年の報恩講が、例年と同様、土曜・日曜の一昼夜にわたり厳修されましたことは、わたくしども蓮光寺門徒一同、大きな喜びとするところでございます。
如来の御尊前、宗祖の御影前に、御満座の結願いたしましたことをご報告するにあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなさまに一言御礼を申し上げます。
ご法中のみなさまにおかれましては、懇ろなるお勤めを賜りまことにありがとうございました。勤行は一昨年より同朋奉讃式によることとなっておりますが、馴染み深い節に合わせてお勤めさせていただいたことでございます。
昨日の大逮夜法要では、「生きることへの意味づけ・価値づけからの解放 —かけがえのない存在の回復—」の講題で当山住職の法話を聴聞いたしました。
経済至上主義がはびこり、生産性の有無により物ばかりか人間までをも振り分けて行こうとする時代にあって、わたくしたちのいのちの存在そのものの尊さに目覚めよとの如来の呼びかけに、このたびもまた導いていただいたことでございます。
また、3年越しでようやく実現した報恩講の夕べでは、奈良県高取町より、本願寺派教恩寺のご住職でシンガー・ソングライターのやなせななさんにお越しいただき、お歌とお話をお聞かせいただきました。
ご自身の体験やご友人との関わりの中で紡がれたことばの数々が、美しい歌声と相まって心に沁みたことでございます。
本日、晨朝のお勤めでは、蓮光寺衆徒の櫻橋さんと前坊守に感話をいただきました。僧俗相集い、ざっくばらんにことばを交わすことのできる空間がここに存在することをあらためて感じたことでございます。
また、満日中の法要では、岐阜県垂井町より、寶光寺ご住職の林憲淳先生にご出講いただき「人の執心、自力の心」の講題でご法話をたまわりました。
縁によって心を散り散りにし自己を失ってしまうわたくしたちが、本願念仏のみ教えをいただき、自己を定める契機をいただくことこそが、聖人のご法事である報恩講の本義であるとうかがいました。
聖人のご生涯にたずねるお話をうかがいましたが、人々との交わりを通じ人間存在の本質を学ばれながら、自らもまた善に迷われた聖人の歩みを知るにつれ、無明の闇の内にあるわたくしたちに、聖人の説き開かれた本願念仏のみ教えが強く深く響くことを感じたことでございます。
さて、今年の報恩講は、困難な状況のもとにありながら一昼夜でのべ百名を超えるみなさまにおまいりいただくことがかなったものと思います。わたくしはあいにく仕事の都合によりオンラインでのおまいりとさせていただきましたが、本堂に大勢のご門徒にご参集いただけることはまことによろこばしいことと存じております。
昨日来、たびたび触れられておりますが、この一年を振り返っただけでもご法縁をいただいた多くの方がお浄土に還られました。わたくしどもの大切な仲間、釋一道=篠﨑一朗さんもそのお一人です。昨日のご法話の中で住職は、篠崎さんの「阿弥陀様の前に座る厳かな空間というか『場』は、聞法するお仲間のお導きや交流もあって、人間を育てていくのだと実感させていただいています 」ということばを紹介しております。
蓮光寺がそのような空間、そのような場として存続しうるかどうかは、新型コロナウイルスの感染という厳しい現実を抱えた今をいかに乗り切るかにかかっております。この法灯を未来の人々に繋ぐため、ますます努力してまいらねばなりません。
住職、坊守を先頭に、門徒一同、今後とも、念仏三昧・聞法精進の道を歩んでまいりますので、ご出仕・ご出講のみなさま方には、変わらぬご指導とご鞭撻をたまわりたく、伏してお願い申し上げる次第でございます。
2022年の蓮光寺報恩講のご満座結願にあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなみなさまに重ねて御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。
このたびはまことにありがとうございました。
蓮光寺報恩講2022 大逮夜法要法話 11月5日(土)
2023年3月14日公開
「生きることの意味づけ・価値づけからの解放
今回の法話のテーマについて
ようこそ、お参りいただきました。まだ人数制限をしての報恩講ですが、今年は人数を多少オーバーしまして、50名以上の参詣をいただきました。Zoomでの参加もいただいております。明日の結願日中も同じような参詣数で、コロナ下において、一昨年より昨年、昨年より今年と参詣者が増えてまいりましたことはまことにありがたいことと思います。親鸞聖人の御恩に応えるということは聴聞ひとつに極まります。ごいっしょに親鸞聖人が明らかにされた本願念仏の教えを聴聞してまいりたいと思います。
さて、仏教、殊に浄土真宗の教えは人間の自我を問題としているのです。自我というと難しいように聞こえますが、自分の思いとか自分の考え方、ものさしと言ったらいいでしょうか。もっと簡単に言うと「私」ということです。「私」と言ったら、それは自我といっていいでしょう。
自我は分別をしますから、意味があるかないか、価値があるかないか、役に立つか立たないと、日々自分にとって都合のいいものばかりを追い求め、思い通りになることばかりを考えていますから、かえって自分というものがわからなくなってくるのです。自我は常に迷いの構造と差別の構造を持ち合わせています。いつも申し上げていますが、特に近現代に入ってからは、自我が絶対化され、人間そのものを深く問うということがほとんどなくなってしまいました。
今日のテーマは「生きることへの意味づけ・価値づけからの解放」です。このテーマは、ずっと私の大きな課題なっているので、寺の聞法会でも時折お話ししていますので、お聞きになっているご門徒もおられると思います。「意味」というのは幅広く使われており、例えば、この漢字の意味は何ですかという使い方は別に問題ありません。ただ「生きることの意味」ということになると、やっかいな問題になります。さらに意味を固定化させるような「意味づけ」、この「づけ」が大問題なのです。
さらに言えば、「生きることへの~」の前に、「自我による」をつけたほうがはっきりしますね。やはり自我の問題に極まるわけです。そして副題は「かけがえのない存在の回復」です。生きることへの意味づけ、価値づけから解放されて、かけがえのない存在として生きることが私たちの大切な課題だということですね。
存在根拠の喪失
『大無量寿経』に「吾当に世において無上尊となるべし」とあります。「無上」とは比較を超えているということです。誰もが比較を超えて尊い、かけがえのない存在であるということです。私たちは、さまざまな縁によって、かけがえのない存在として生まれてきたのに、現実は、存在よりも何ができるかという行為が優先されています。特に経済至上主義のなかで生産性があれば生きる意味があるという現代の価値観に大きな問題があります。生産性があれば生きる意味があり、それを失えば意味がないという風潮が誰の上にも多かれ少なかれ蔓延し、かけがえのない存在、尊さが見失われているのではないでしょうか。
生きることの意味を経済にからめて考えると、簡単に言えば、使えるか、使えないかで、生きる意味づけ、価値づけをしていくということなのです。行為で人間の生きることへ意味、それも生産性に規定されて、労働力の担い手として経済的価値で人間の優劣が決められてしまいます。ですから、何か役割を果たすことで、それを自分として、自分の存在意義にしていくのです。「責任を果たす主体」を自分として生きることをアイデンティティの確立などと言われていますが、ここでいう「自分・自己」とは、経済社会のなかで評価される自己を指すのです。意味づけ、価値づけ、条件づけに適合した自分、それは立場を自己としているだけで、自分に付加価値をつけて、他人が自分をどう評価しているかが最大の関心事になってしまっています。評価される自己、それは自分なのでしょうか。自分でないものを自分として生きているのではないでしょうか。なぜなら、うまくいっているうちはいいですが、うまくいかなくなると自己責任として問われ、見捨てられてしまうのです。そうすると自分がなくなってしまうような錯覚が起こしてしまうのです。
そして「生まれてきた意味はない。生まれてこなければよかった」ということになっていくのです。
くり返しますが、その背景にはどんな人間も、かけがえのない存在ということが忘れ去られているのです。自我によって、かけがえのないいのちが見失われているということは、存在根拠、真のよりどころをもっていないのが多くの現代人ではないかと思うのです。ここに存在の孤独という問題があります。
こうして生きることの意味を求めて迷い続けている私たちを解放し、その私たちのあり方が愚かな凡夫であると気づきを与え、その気づきを通して生きる意欲(本願の意欲)を与えて、かけがえのないいのち、存在の尊さに帰らしめるのが、阿弥陀さんの教えなのですが、なかなか受け取れないのです。それほど自我は根深いのです。
人間の自我分別によって、生きることの意味づけや価値づけをしてしまうと、そうでない人、そこからもれてしまう人は生きている意味がないのでしょうか。生まれたことの意味はないということなのでしょうか。大問題です。
親鸞聖人が顕らかにされた阿弥陀さんの教えは、無分別の世界です。私たちみたいに分別はしないのです。無条件の世界、ありのまま、そのままの世界です。どんな人も、もっと言えば、動植物もみな存在そのものが尊いと教えられています。
私たちのいのちはどこから始まったかわからないぐらい、無始以来のいのちの営みのなかで、奇跡ともいうべく何一つ無駄もなくこの私になって生きているわけです。ですから人間も動植物もその大きないのちの世界から生まれて来た。無分別の無量寿の世界から生まれて来た。だからどのいのちも尊いのです。ところが人間だけが自我分別を持ってしまった。なぜでしょうかね。これは解明できませんけれども、でも自我分別を持ってしまったからこそ、迷いの私に気づかされて、懺悔(さんげ)と御恩を感じて生きていくことができるのは人間だけなのです。しかし、このことがなかなかいただけないのです。それぐらい私たちの自我はやっかいなのです。
今、ロシアがウクライナを侵略しています。戦争はいけないと言いながら、戦争を続けてきたのは人間なのです。そのうえ、核を広げてはいけないということが「善」として叫ばれていたのに、核を持たないと国を守れないから、核を保有することが「善」になりつつあります。人間の自我は、縁によって善悪の基準をコロコロ変えていくのです。まさに業縁を生きる愚かな凡夫です。そのことに気づかされないと、戦争はけっしてなくならないでしょう。自我では戦争をやめることはできないのではないでしょうか。人間に正義などないのです。そして、ここにも生きることへの意味づけ、価値づけがなされているのです。
罪福心と真実信心
自我で教えを聞けば、それはすべて罪福心です。宮戸道雄先生は「罪福心とは、災いをおそれ、幸福を招こうとする心で、自我の投影だ」と教えてくださいました。阿弥陀さんの教えはその自我を翻す教えです。ですから、思わず、教えが聞こえてくる、頭が下がるということがおこるかどうかですね。そこには自我が介在しないのです。
誰もが大きな病気に罹れば、完治しますようにと祈らざるを得ませんが、これは、やはり罪福心ですね。完治しても、病気をする身であることは何も変わらないのです。また病気をするのです。ですから阿弥陀さんの教えは、病気であっても、けっしてかけがえのない存在を失わずして、ありのままの自分を生きる力を与えてくださる。ただ治ってよかったという話ではなくのです。「病気をする身であっても、かけがえのない存在を失わずして生きるということがあるから、病気が治れば、それを本当に喜べるのです」と宮城顗先生のご著書に書かれておりました。私たちが求める宗教心はすべて罪福信です。ですから私たちが求める宗教心ではなく、私たちに求められる宗教心が本願念仏、つまり真実信心なのでしょう。だから教えが聞こえてくるとか、身に響くとか、そういう受け止めになるのです。
親鸞聖人は、本当に「救われがたき身である」と教えてくださいます。この人間の相(すがた)を「罪悪深重の凡夫」だと教えられてきたわけです。救われがたい身であることが救いに与る。論理的に矛盾しているようですが、要するに、救われがたき身であるとうなずかされたということは、真実にふれたからです。自分の今のあり方では救われないのだということが気づかされるのです。
親鸞聖人が凡夫の身である自分について、こう表現されています。「いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」という『歎異抄』第2章のお言葉です。
本来、どのような努力によっても、仏になることのできない身でありますから、どうもがいても地獄は私の必然的な居場所なのです。地獄が自分の必然的な居場所というのは絶望して言われているのではありません。また努力は無駄と言っているわけでもなく、凡夫性の深さを表現しているのです。地獄が必然的居場所と受け止めているということは、実は親鸞聖人の中から地獄は消え去っているのです。阿弥陀さんの呼びかけによって、自分の正体に気づかされ、その自分を受け止めたということです。それが教えが聞こえてきたということなのです。ですから、照らされた凡夫なのです。これが私たちに求められる宗教心(真実信心)なのです。
親鸞聖人から地獄が消え去っているということは、安田理深先生のお言葉で言えば、夢を見る必要もないし、絶望する必要もない、という世界をたまわっているのですね。そういう凡夫の自覚が、この言葉に表れていることを感じます。
親鸞聖人も比叡山で20年間も修行努力されたのです。一年や二年で山を下りたわけではありません。20年間修業をしても煩悩はなくならないのです。ですから、親鸞聖人ほど人間の正体を誤魔化さなかった宗教者はいないのではないかと思います。そして法然上人お念仏の教えに出遇われるわけです。
ですから、深い煩悩性に目覚めて、自分から出発する仏教から、本願から出発する仏教への転換が親鸞聖人の中に起こったのです。自分の思いが転じられて、阿弥陀さんの眼から人生を見直していくような、そういうような方向性が生まれてくるわけです。真宗の教えの要は、機法二種深信だと思いますね。機(阿弥陀さんの教化の対象となる衆生)の自覚からいえば救われない身であるけれども、法の上から言ったら救われがたき身と自覚することを通して本願の救いにあずかっていくのだと。そういうことだと思いますね。ですから、自我分別をやめて救われるということではないのです。自我分別を抱えたままで、それを超えた無分別(そのまま、ありのまま、無条件)の阿弥陀さんの本願念仏の世界(浄土)が私の上に開かれてくるのです。
人間関係の喪失と存在の孤独
一人ひとりがかけがえのない存在なのですが、生きることへの意味づけ・価値づけは、本来の人間関係をさらに崩壊させていきます。これにコロナがからんで益々関係性が見えなくなっていきます。
以前から、立てこもり事件はありましたが、ここ数年、数十件の立てこもり事件が起きています。ああいう立てこもり事件は、計画性がなく、単独犯行なのですが、必ず人を巻き込んでいくのです。事件を起こす背景に、定職がないとか、学力が上がらないなど、まさに、経済的価値による人間の優劣によって、生きることの意味づけから放り出された人が多いことが感じられます。
一つ代表的な例を挙げておきます。今年の1月に東京の渋谷の焼肉屋の立てこもり事件を起こした青年の言葉です。端的に言うと「生きている意味が見いだせず、人生に絶望したことが動機です」。この青年は、すごく真面目な人間だと報道されていました。どうもバイト生活をしていて、東京に職を探しに来たのだけれど見つからなかったのでしょう。だから「死刑になるために、立てこもり事件をおこして警察につかまろうと思った」ようです。彼は、焼き肉屋で悪さをする気はなく、悪さをするようにみせかけて捕まろうと思ったのでしょう。ですから彼は執行猶予で済んでいます。
しかし、なぜ人を巻き込むのでしょうか。彼を対象化してみるのではなく、私たちも縁さえあれば、彼と同じような気持ちになるかもしれません。それが人間なのです。まさに業縁存在です。
私が感じることですが、一つは「状況の孤独」ということがあります。彼の状況は孤独なのです。だから人との交わりの中でと考えたのかもしれません。しかし、その根には「存在の孤独」という問題があるのです。なぜなら、裸の王様と化した自我を絶対化して生きていますが、その自我が、人間の真の存在根拠にならないからです。
それから、「世間を恨んでいる」ということがあります。これは、むしろ秋葉原事件の犯人にあてはまるのかもしれません。勉強ばかりさせられ、人間関係が構築できず、SNSでも馬鹿にされて社会を恨んだわけです。また、学力が東大のレベルに上がらないから、東大前で受験生などを刺傷させた若者もいましたね。
そしてもう一つ、以前リストカットということが問題になりましたが、リストカットをすることによって、自分が生きているという実感が得られたのですね。そういう点から言えば、死刑になる前に、人を巻き込んで事件を起こすことによって生きている感覚を持ちたいと考えたのかもしれません。しかし、孤独であり、世間を恨み、生きている実感がないというのは、多かれ少なかれ、現代人が抱えている問題なのではないでしょうか。
その後、知ったのですが、焼き肉屋に立てこもった彼は「一時的に生きたというか、こういう人生を送ってしまったということを残したい」と言っていたのです。あとは警察に捕まって人生を終わりにしたかった。死んでしまいたかったということでしょう。3番目の理由でしたが、それ一色というわけでもないかと思います。いずれにしても生きている実感がないということは大変な問題です。「なんで生きているのか」と尋ねられると、ちょっとあとずさりしてしまいませんか。他人事ではありませんね。
一昨年でしたか、相模原事件のことをお話ししましたが、「障がい者は生産性がなく家畜同然だから、安楽死させろ」と生きることの意味づけをしてしまうと、そこまでできてしまう社会になってしまっています。いのちの峻別が行われているのです。
本当に、私たちは生まれた時から、「何ができるか」という行為に急き立てられて生きていて、存在そのものの尊さを学ぶことがほとんどなかったと痛感します。
別に悪いことではありませんが「大人になったら何になりたい」と言われたことがありますよね。また、そういうことを言ったりしていますね。悪いことではありませんが、やはり、気をつけないと、社会のレールに乗った言葉になってしまいます。
今日も出仕をしてくださったTさんが、ある学習会でしみじみ語っていたことを思い出しました。小学校でTさんの息子さんが、担任の先生に「あなたは将来何になりたいの?」と聞かれ、答えなかったそうです。帰宅してり、ご両親に「先生にああ言われたけど、特に何もなりたくないから困ってしまった。すぐ何になりたいって聞かれるんだ」と言ったそうです。私はそれを聞いて、Tさんの息子さんのほうが自然だと共感しましたね。それでいいのではないですか。もう10年以上前になりますか、朝日新聞の投書に「君は何になりたいですか」と尋ねられた5歳の男の子は、「僕は何にもならないよ。僕は僕になるんだ。」と答えました。当時大きな反響がありましたね。この男の子は、かけがえのない存在として大事に育てられたんでしょうね。まず存在ということがしっかりあって初めて行為ができるのではないでしょうか。存在の確かさがないところで行為をしてもむなしくなるだけではないでしょうか。男の子の言葉は、「うまくいってもいかなくても、すべてそれがありのままの僕なんだ」と聞こえます。子どもながら、存在根拠がしっかりしていますね。私たちの言葉で言えば、如来のいのちの世界に支えられ生かされているということでしょう。
『PLAN(プラン)75』の映画から教えられること
ところで、これだけ少子化が進んで超高齢化社会になっていくと、人間関係の歪みがさらに増してきます。非寛容な社会がさらに進んでいます。
そんな日本の近未来を描いた『PLAN(プラン)75』という映画が6月から8月にかけて上映されました。私も観ました。早川千絵さんという方が監督で、カンヌ国際映画祭の入賞作品にもなりました。こんな大切な映画は、ぜひ若い人といっしょに観てほしいのです。というより、若い人こそ観てほしい映画です。
「PLAN75」という名前から何が想像できますか。実は、75歳になったら死を選べる制度ができ、それをリアルに描いた映画です。死を選ぶということは、使えない人間には生きる意味がないということが「意味づけ」されていることが背景にあるのです。あきらかにいのちの峻別です。
倍賞千恵子さんが主役で、彼女はホテルの掃除婦として働いていましたが、同年代の人が掃除をしながら倒れてしまったことがきっかけとなって、年寄りはいらんと、ホテル側から年配の掃除婦が解雇されるのです。もちろん倍賞さんもその一人でした。彼女は子どもがいないし、夫は亡くなっていて、一人で生活していたので、なんとしても働かなければならないのです。一生懸命職を探すのですが、見つからない。それで「PLAN75」に応募してしまうのです。死ぬまでの間に、楽しいこととかいろんなことをスタッフがサポートしてあげるのです。そして死ぬ時期を決心した時に、要するに安楽死です(安楽死や尊厳死の世界共通の定義や概念はありません)。ベッドに横になって管をつけられて、死に至るための何か薬物を入れられているのでしょう。こうして高齢者が死んでいくのです。ところがこの制度に関わった若いスタッフたちが次々と疑問を感じていくのです。倍賞さんを担当した若い女性スタッフは、倍賞さんが死を選択した日に、必死に止めようと電話をするのですが、つながらなかった。この女性スタッフはがっくり肩を落とすのです。このように高齢者と接したこの女性スタッフは、いのちの尊さを痛感していくのです。
また別の若い男性スタッフは、20年来会ってなかった叔父、自分の父親の弟ですよね。父親の葬式にもこなかった叔父さんですが、「PLAN75」に応募してきたのです。親族関係にあるから、その叔父の担当はできなかったけれども、個人的に叔父と接していくうちに、叔父が死んでいくことについて、だんだん疑問を持つようになっていくのです。安楽死した叔父は、集団火葬されるのです。彼は、せめて集団火葬はさせたくないと、叔父の遺体を車に乗せて火葬場に向かうのです。
このように 「PLAN75」の若いスタッフたちが、存在の尊さを痛感していくのです。倍賞さんは自分から管を抜いて、生きようと、「PLAN75」から去っていき、夕日を眺めながら歌を歌っているところで映画が終わるのです。そろそろYouTubeやアマゾンプライムなどで上映されるかもしれませんので、ぜひ視聴してください。
この映画を通じて、早川千絵監督は何を伝えたかったか、もうおわかりだと思います。
早川さんは「社会的に弱い立場にいる人に差別的な発言があったり、自己責任という言葉が幅をきかせたりして、なかなか人に助けを求められない社会になっている実感があるので、生きている価値とか意味ではなく、生きていること自体が尊いということを伝えたかった」と力説されています。「生きている価値とか意味ではなく、生きていること自体が尊い」とはっきり言い切られています。「無上尊」ですね。どのいのちもつながり合い支え合っていかされているのです。自我を超えた真実が早川さんの上にはたらき出ているように感じます。この映画は非常に現代の歪みとつながっている内容ですから 、どんな人たちも実感できる映画なのです。
早川さんは、阿弥陀さんという言葉を使っているわけではないけれども、真実のはたらきというものを感ずる人がやっぱりいるのですね。自我だけでは、早川さんの言うようなことは、言えないと思いますね。人間は愚かさに対する懺悔というか、早川さん自身が感じていないと、こういう映画は作れないと思います。意味つけや価値づけによって、生死流転(迷い続けること)している衆生を解放していくのは、生きていること自体が尊いということに目覚めることなのだということが強烈に伝わってきます。ですから浄土真宗の人であるかないかは全然問題ではないのです。
私たちにとって、存在の尊さを回復していくには、教えに生きている人、やはり得道の人に遇うことが大切です。 聴聞し、得道の人に遇うことを大切にしていきたいものです。
作家青木新門さんの生きざま
これに関連して、世の中ではじき者になっても存在根拠を持っていれば生きていけるということを証明した作家の青木新門さんが8月6日に亡くなったのです。すぐ弔電打ちました。お別れ会は都合がつかず失礼しました。青木新門さんとはもう20年来のお付き合いで、このお寺にも4、5回も来ていただきました。『納棺夫日記』が代表作品で、映画『おくりびと』はこの本が原版として制作されました。でも新門さんは『おくりびと』で自分の名前を出なさいでほしいと言ったそうです。なぜかというと「いのちのバトンタッチ」が描かれていなかったからです。でも新門さんを尊敬する本木雅弘君(もっくん)によって、その名を広く世に知られることになります。真宗の葬儀はいのちのバトンタッチです。私の中に亡くなった父の存在が生きているということは、いのちのバトンタッチをしているからです。
NHK「こころの時代」の番組を収録する時に、インタビュア金光寿郎さん(2020年1月還浄)が、「新門さんとのインタビューはお寺が似合う」と言われ、新門さんが「では、東京の亀有の蓮光寺でやりましょう」ということで、うちの寺で収録しました。見に来た人もいるかと思いますけれども、まだホームページに載っていますから、関心のある人は見てください。
新門さんのすごいところは、仏法を知的理解せず、生活の中からいただいていった人なのです。その新門さんも、生きることの意味づけ、価値づけという点で言えば、世の中に見捨てられた人なのです。それがどのように存在根拠を持ったかということですね。彼は失業中に、好きな人ができて子供が生まれました。だからすぐにでも仕事を探さなければなりません。これも縁ですね。たまたま新聞を見たら、葬儀社が社員を募集していたのです。そして入社しました。職務は、遺体を洗うことでした。納棺夫という名前は彼の時につけられたのではないかと記憶しています。
富山というと真宗王国ですが、真宗だけではなく色々な宗派も俗信もあります。それで新門さんが遺体を洗う仕事をはじめたことで親戚は総スカン。付き合っていた人も離れていくんです。死をタブー視している社会、そこには死に対する穢れ感などを持ち合わせていますから、遺体を洗う新門さんから遠ざかっていったのです。何も悪いことをしていないのにつらかったのだと思います。
ところがそこに自分の存在を丸ごと包むそういう世界に次々出遇っていって、その世界は、実は親鸞聖人が最初から言っていたことだったと、あとからそれは気がつくのです。
『納棺夫日記』に「人を恨み、自分の不遇を恨み、すべてが他者の所為だと思っていた人間が、己をまるごと認めてくれるものがこの世にあると分かっただけで生きていける。死をタブー視する社会通念を云々していながら、自分自身その社会通念の延長線上にいることに気づいていなかった。」
こう自覚された最初の出遇いは、昔の彼女のお父さんの遺体を洗っていた時のことです。新門さんもお金のためにいやいやしていた仕事でしたが、遺体を洗いながら汗がぽたぽたしたたりおちてくるのです。それを彼女が、そっと新門さんの汗を拭き続けてくれ、洗い終わると丁寧に新門さんにお礼を言われたのです。遺体を洗うことで差別を受けていた新門さんにとって、彼女は死穢などまるで感じずに、父の体を洗ってくれる新門さんに感謝の気持ちをもって汗を拭いてくれたのです。そこには交換条件も、取引もありません。自分が無条件に包まれている世界に出遇い、それだけで生きていけると感じられたのです。存在根拠をいただいたわけです。実は、その部屋には、死の穢れなど一切ない世界である浄土を新門さんは感じ取ったのです。このはたらきが阿弥陀さんだったということはあとから知るのです。それだけにとどまらず、世間を恨んでいた自分も社会通念の延長上で生きていたことに気づかされ、愚かな凡夫と自覚されたのです。
「自分の全存在を丸ごと認めてくれるものに出遇うと生きていける」新門さんは何というすばらしい世界を賜ったのでしょうか。現代の社会はまるごと認めるという力が弱くなっているのではないでしょうか。
今まで、普段着で遺体を洗っていた新門さんが、ネクタイをして白衣を着てアタッシュケースを持っていくようになったのです。死は人間が必ず通る道であり尊いお姿といただいて、亡くなった人を丁寧に拭くのです。
その後の新門さんは「死者の顔が光って見えた」とおっしゃっています。光っているというのはピカッと光っているわけじゃないです。光とは自我がひっくり返るということです。「正信偈」にも十二光が出てまいりますね。十二の光明は、阿弥陀さんの智慧のはたらきですね。新門さんは、遺体を洗うたびに愚かな自分が照らされていたのです。さらに「蛆も生命なのだ、蛆も光って見えた」と書いてあります。死後、何日か経ったおばあちゃんの遺体を洗いに行ったときに、もう蛆がわいていたんですね。普通なら汚いと思うでしょう。ところが蛆も繋がり合ったいのちだと新門さんは教えられたのです。つながり合い支え合ったいのちの世界。無条件のいのちの世界。そう感じると蛆たちも光って見えたのです。
新門さんは「死者の顔が光っていた、蛆(うじ)も生命なのだ。そう思うと蛆たちが光って見えた。死者たちの顔の光顔巍巍(こうげんぎぎ)たる様子に気づくまで仏法に出遇うことがなかった。『大無量寿経』にある如来の光顔巍巍の様子と阿難がその光に気づいたことを如来が褒めたというそのことだけで、親鸞聖人はこの『大無量寿経』を真実の教えであると断定される。私は、この親鸞聖人のとらえ方に、言い知れぬ感動を覚えました。そして親鸞聖人の思想が、実践に裏打ちされていることを確信しました。どんなことがあっても平気で生きていける(ありのままの自分を生きる)ということは、光に出遇う、つまり自我(自分の思い)がひっくり返るということがなければ言えません。それは阿弥陀さんと共にあるからできるのであって、自分の力ではけっしてできないのです。」と語っておられました。
新門さんは、苦悩を通して、阿弥陀さんの教えに出遇い、真の存在根拠を与えられた人生でした。
新門さんが一番嫌いな親戚のボスのおじさんが危篤となり、しぶしぶお見舞いに行ったら、ちょうど目がさめていて、そのおじさんは新門さんに手を差し伸べて「ありがとう」と言われました。自分が死を受け入れたときに、死の穢れが消えていたのでしょう。だから嫌っていた新門さんに「ありがとう」と言ったのでしょう。新門さんは「おじさん、ごめんなさい」と土下座したそうです。それは自分も死をタブー視していた人間の一人であり、おじさんを恨むどころか、死を受け入れたもの同士が感応道交する世界が開かれていたのでしょう。どっちがいい、どっちが悪いという自我世界を超えています。病室はまさに浄土の世界でありました。
「生と死が限りなく近づくか、あるいは生きていながら死を百パーセント受け入れられたときに、まったく今まで見えていた世界と違う世界、蛆も砂利も雑草もあらゆるものが光って見える世界(つながり合ういのちの世界)が眼前にあらわれるのではないでしょうか。そのとき、人は必ず柔和になって、必ず『ありがとう』という言葉が出てくるのですね」と新門さんは語っておられました。
ですから、葬儀はいのちのつながりを感じ、いのちのバトンタッチをするところです。例えて言うと、駅伝で、あれはタスキですけれども、一人の先頭ランナーが走っても、そのランナーの人生があって、そのランナーを支える人、いろんな人がタスキにこめられている。そのいのちのタスキを次のランナーが受け継ぎ、最後にアンカーがそのいのちを全部いただいて走り抜くんでしょう。こういういのちのつながりの中に私たちは生かされているわけです。ですから死とはいのち存在の故郷である浄土に還っていくことですが、新門さんの存在は私の中に生き続けています。なぜなら私のいのちは如来のいのち世界(浄土)とつながっているからです。
自分の存在に感動して、人生を全うした篠﨑一郎さん
この5年間で同年代の大切な法友が2人亡くなりました。一人は田口弘さんでもう何度もお話をさせていただいております。そして、もう一人は、住職の片腕と言われた篠﨑一朗さんです。今年の6月10日に63歳で浄土に還られました。代々蓮光寺の門徒で、念仏者のおばさんに影響を受けた方です。念仏相続は大切ですね。蓮光寺の教化委員幹事として、私を支え、多くの人に影響を与えた人です。篠﨑さんは37歳の時にステージ4の末期の胃がんが発見され、生存率が0%に近い状況だったでしょうか、有名な病院のお医者さんですら「1年間、自由に楽しませてあげてください」と言われたほどです。とにかく必死に治療に専念され、ホリスティック医学の第一人者の帯津良一先生とも出遇い、奇跡的に快復されました。その時は治療で頭がいっぱいで、もし亡くなっても阿弥陀さんが救ってくれるだろうという程度にしか考えられなかったそうです。
しかし快復後、再発の危険性が非常に高かったので、この不安が篠﨑さんを聞法の世界に呼び寄せたと言ってもいいかもしれません。不安の中で聞法を続けていくうちに、彼は大切なことを教えからいただいたのです。再発の不安の中で、阿弥陀さんの教えが響いてきました。癌生活から阿弥陀さんの教えとの出遇いを書き綴った『人生に何一つ無駄はない』(東本願寺出版)は多くの癌患者が阿弥陀さんの教えにふれる縁を生み出し、どんな人生を歩もうとも、かけがえのない人生を生き抜く相(すがた)を私たちに示してくださいました。「どんな状況にあっても、だれにも代わってもらえない、代わる必要のない、尊い存在として、そのままの私を引き受けよ」という阿弥陀さんからの呼びかけをよりどころとして、聞法ひとすじの人生でした。
篠﨑さんは昨年6月以降急激に体調が低下し、酸素吸入の生活を余儀なくされました。今まで年中お寺に顔を出していたことが適わなくなり、それでも一番大切な報恩講に一座だけでも参詣したいと、なんとか大逮夜法要だけ対面で参加してくださいました。
報恩講の準備も運営にも携わることができない悔しさもあったでしょうが、篠崎さんは「そこで感じたことは、今まで当然と思っていたことが、こんなにも有難い事だったんだと再認識させられたことです。大逮夜法要や法話のリアル参列の空間というか、その空気は何にもまして厳かな気にさせられ、一年を振りかえり、自分の置かれた現在の身が不自由を抱えながらも、こうやって蓮光寺の阿弥陀様の前に立つ厳かな空間という〝場〟が、人間を育てていくのだと実感させていただきました」と語られています。
この言葉は、篠崎さんとの出遇い直しを通して、その真意が明らかになってきました。まちがいなく、篠崎さんは最後の報恩講になるという覚悟で参詣に来られました。蓮光寺の本堂という場で、いっしょに聞法してきた法友と語り合うことで、自分の人生を振り返り、どんなぼろぼろになった自分でも、やっぱり阿弥陀さんはそのまま受け止めてくださる。だから、今の自分のままで「これでよし」という深い感動を覚えたのでしょう。「人生に何も無駄はない」ということを、報恩講でいただき直した篠崎さんの慶びの相(すがた)が目に浮かびます。阿弥陀さんの願いに生きた篠﨑さの死は、生の円成、やはり存在の成就であったと教えられました。これからも篠崎さんとともに生きていきたいと強く感じたことです。
篠崎さんは真宗門徒ですが、早川千絵さんのように、やはり自我を翻す世界をもっている人がいますから、如来は一切衆生にはたらきかけていると思うわけです。如来は群生海の心ですからね。苦悩するすべての人間の上に本願がはたらいているのですね
くり返しますが、生きること(意味づけ、価値づけをして、迷い続けている私たちを解放し、その私たちの在り方が愚かな凡夫であると気づきを与え、その気づきを通して生きる意欲(本願の意欲)を与えて、存在の尊さに帰らしめるのが、阿弥陀さんの教えなのです。
今日のテーマの総括は、志慶眞先生のお言葉、これに尽きると思います。「如来の呼びかけに出遇うことによって、自分の思い、つまり『意味』を超えた世界が開かれるのです。私も長年、何が問題かということがわからないまま『意味』を求めて苦しんできました。しかし仏教にうなずくということは、意味を求める必要のない、そのままでいいという世界が開かれるということだったんです。その如来のはたらきに支えられ育まれ生かされていることに目が覚めた時、苦悩の人生は生きるに値すると確信しました」
苦悩の人生は生きるに値するんだと。素晴らしいですね。苦悩するということが本願に出遇っていくことなのです。自我分別の上に本願の世界、浄土が開かれてくるのです。誰もが意味を超えて、存在の尊さを感じられるということを私は確信したということは、自分が救われるということは、全ての人が救われているということなのです。個人の救いではない。一切衆生の救いが阿弥陀さんの願いなのです。
ですから「吾(われ)当(まさ)に世において無上尊となるべし」と、『大無量寿経』に教えの要が述べられているのです。
安田理深先生「いちいちの衆生に唯我独尊の自覚を与える、それが仏教です」と言い切られておられます。ただ私が一人尊いというのは、つながり合って、支えあっているいのちですから。どのいのちも尊いということですね。それが私自身の上に感じるということでしょう。その自覚が与えられることが仏教です。困ったことが困らなくなるとか、そういうことは一言も言ってない。どこまでも苦悩の人生を、罪悪深重の凡夫と自覚することを通して、生きる意欲が与えられてくる。それは存在の尊さ、どんな状況にあっても見失うことはない、そういう世界を賜わり続けるということでしょう。終わりなき歩みをさせていただくことが大切ですね。
慶讃テーマと御遠忌テーマ
来年の3月、4月に「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要」が本山で厳修されますが、「南無阿弥陀仏 人と生まれたこと意味をたずねていこう」が慶讃テーマとなっています。この慶讃テーマですが、当初、私自身、これを見たときピンとこなかったというのが正直なところです。うちのお寺の聞法会でも、門徒さんが聞法を通して様々な受け止めをされております。その受け止めのいくつかを紹介しますと、「南無阿弥陀仏は、意味を超えた教えではないのか。意味がある、ないは人間の分別から出てくる言葉であるから、無分別の南無阿弥陀仏の教えが人間に意味を与えるということはないのではないか」
この受け止めは志慶眞先生の言葉に通底していますね。それから「念仏は自我の闇を照らし、自我を翻していく教えだから、人間に自覚を与えるのではないか」などです。
テーマに対して疑問や問いを持つことは大切なことです。では一体、この慶讃テーマは何を呼びかけているのか、さらに聞法を通して、明らかにしていくことが大切ですし、今日の私の法話からも、皆さん、感じられたことがあるのではないかと思います。
同朋新聞に連載されている「人間といういのちの相」の願いは、このテーマと宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌テーマ「いのちがあなたを生きている」の学びを深めるためと書かれています。一見、まったくちがったテーマに見えるのですが、この二つのテーマは深い不離の関係にあるということです。
意味(づけ)を求めて生きざるを得ない人間の関心に大悲をもって寄り添って、「人と生まれたことの意味をたずねていこう」と阿弥陀さん(南無阿弥陀仏)が呼びかける。そうすると、私たちは「阿弥陀さんは、何か意味をあたえてくれるのだろうか」と教えに訪ねていく。ところが教えを聞いていくうちに、阿弥陀さんは私たちに意味を与えてくださるのではなかったと気がつかされていくのです。それによって、意味(づけ)において流転する「機」があぶりだされ、「今、いのちがあなたを生きている」の世界に私たちを帰らしめてくださるのです。
「今、いのちがあなたを生きている」、このいのちは如来のいのち(本願念仏)といただいています。そこにうなずくかは一人ひとりの課題ですが。本願が私の主体となってくださるのですが、私たちはどこまでも自我分別をもった凡夫です。私が阿弥陀さんになるのではない。ここはまちがえてはなりませんね。曽我量深先生は「如来は我なり、我は如来にあらず。如来、我となって我を救いたもう」と的確に述べられておられます。無分別の世界にふれて、凡夫の自覚を通して、ありのまま、そのままの私を生き抜くていく力を賜る。それが「今、いのちがあなたを生きている」ということですね。ですから、意味(づけ)や価値(づけ)において、迷い続ける人間を、そこから解放し、凡夫の自覚を通して、かけがえのないいのちを生き切る意欲が与えられること、まさに無上尊をよびかけるのです。阿弥陀さんが意味を与えるなら、その意味からもれた人たちはどうなるのでしょうか。阿弥陀さんは、人間に意味を与えることはありません。
私たちは、もともと尊い存在として生まれてきていますが、人間は自我分別をもっているがゆえに「生苦」(生まれる苦しみ)を抱えて生まれてきます。だから意味づけや価値づけから一生出られず、意味(づけ)において、生死流転(迷い続けること)をくり返す私たちに、「気づき」、「目覚め」をあたえて、存在の尊さに帰らしめるはたらきが阿弥陀さんの教えです。
ですから、阿弥陀さんは、人間に意味を与えてくださるのではなく、「気づき」と「目覚め」を与えてくださるのです。
私は、慶讃テーマは如来の大悲による善巧(ぜんぎょう)方便とおさえ、方便を通して、宗祖御遠忌テーマに帰せしめるといただいているわけです。方便とは、うそも方便ということではありません。方便とは真実に導く手立てをいうのです。私たちのような凡夫は、方便なくして真実にふれることはできないのです。慶讃テーマと御遠忌テーマの不離の関係を見ればうなずかされることと思います。
「浄土三部経」がそうなっています。真実の教『大無量寿経』(第十八願)から、方便の教『観無量寿経』(第十九願)と『阿弥陀経』(第二十願)が説かれ、人間のあり方に合わせて、『観無量寿経』・『阿弥陀経』を説きながら、最終的に第18願に帰せしめるのです。
慶讃テーマは第十九願の世界であり、如来の大悲による方便(善巧方便)によって、宗祖御遠忌テーマ(第十八願)に帰せしめるのではないでしょうか。
最後は少し難しいことを話しましたが、今後も聞法生活を大切にしていきたいものです。ご清聴ありがとうございました。
蓮光寺報恩講2022 報恩講の夕べ 11月5日(土)
2023年3月26日公開
歌とお話
曲目
夜が明けるよ(オリジナル)
夕焼け小焼け(唱歌)
蜜柑(オリジナル)
故郷(唱歌)
さくら(オリジナル)
星のパパへ(オリジナル)
名もなき花(オリジナル)
恩徳讃
「報恩講の夕べコンサートでお伝えしたかった思い」 やなせなな
早いもので、初めて蓮光寺様でコンサートをさせていただいてから、10年以上の歳月が流れました。
その間には様々な出来事がありましたが、コンサートにお越しくださった皆さまの身の上にも、時の流れの中でいろいろな変化があったことと思います。
おめでたいこと、うれしいこともたくさん起きたことでしょう。しかしながら、ご自身や身近な人が病気に罹ってしまったり、大切な人がお亡くなりになったり…といった悲しい出来事に遭遇する場面も、年齢を重ねれば重ねるほど増えてしまったかもしれません。
私の両親は79歳になり、母は数年前から病気になりました。元気で、働き者で、明るく、頼り甲斐のある大きな存在だった母が、心身のつらさを訴えて床に臥せることが増えたことは、私にとって本当にショックな出来事でした。長年に渡り、親は自分を守ってくれる存在だ、と思い込んでいましたが、気が付くと立場は逆転し、これからは私が親を守ってあげなくてはならないのだということを、しみじみ感じる毎日です。
そんな中、認知症を患った一人の「あなた」と、お世話をする家族の「わたし」を描いた「蜜柑」という楽曲を、今回の報恩講の夕べでも大切に唄いました。この歌を作ったのはもう20年ほど前になります。認知症を患う方々が入所されている施設を慰問コンサートに訪れたことがきっかけで作りました。
当時私は、認知症を患って、いろいろなことを忘れ去ってゆく入所者さんたちの姿を目の当たりにし、悲しいことだと感じたのですが、その気持ちを母に話すと「それはきっと仏様からの贈り物だよ」と言ったのです。
人は生きている中で、大切なものをたくさん得てゆきます。家族、仕事、財産──しかし
、命終える時には、そのどれ一つとして持って行くことはできません。全ての荷物を置いて、何もかもを手放さなくてはならないのです。だからこそ、忘れて、荷物を軽くしてもらっているのだから、それは悪いことではないかもしれないよ、と母は言いました。
私は胸打たれ、少し救われたような気持ちになりました。『蜜柑』は、その時の母の言葉に背中を押されて書いた歌でした。
そう言った母も、最近では少しずつ物忘れが増えてきました。日増しに小さくなる母の背中を見るのは、本当に寂しいのですが、こうして準備をしているのだ、と感じるところもあります。
そして、いつか誰もがその命を終え、先立った人たちと再び会える世界が広がってゆくのかもしれません。
コンサートの後半は、残されたご遺族をモチーフにした楽曲を、エピソードと共にいくつかお届けしました。
最後は『名もなき花』という曲で締めくくりました。私たちもやがては命を終えますが、残してきたこの世では、思いが受け継がれ、また新たな命──“名もなき花”が生まれます。繰り返される命のバトンリレー。そこには、先立った人々がお念仏となり、また、お浄土から届く“名づけられぬ光”となって照らし続けるのだろうと、そんな想いを歌にした曲です。
明日も咲いている 世界を包むように
時は流れ、ひとつとして同じ姿のまま留まるものはありません。限りある尊い今を重ね、味わいながら、生かされている限り、お念仏の中で精一杯この命を生ききっていきたいという想いを分かち合わせていただいた夜でした。
蓮光寺報恩講2022 晨朝法要・感話 11月6日(日)
2023年3月26日公開
櫻橋淳 蓮光寺衆徒・教化委員 (釋淳心)
おはようございます。昨年の7月に、仕事をしていましたら胸が痛くなり、救急車で緊急搬送されました。色々検査をして、なかなか病名がはっきりせず、心臓ではないかとかお医者様も相当悩んだようなのですが、最終的には動脈乖離でした。1週間入院もしたのですが 、病室から出てはいけないと言われました。何か死んでしまうのではないかと思ってしまうぐらい、こんなに痛いものかと思いました。コロナでお見舞いもありませんから、YouTubeで真宗の法話を視聴しておりました。
当時、妻はお腹が大きくなっておりまして、子供が生まれそうだったのですが、退院をして2日後に子供が誕生しました。短い時間の間に生と死を感じたわけです。ですから昨日もそのことを考えながら、住職とやなせななさんのお話を聞いておりました。
3年前、本山に奉仕団に行ったとき、清掃奉仕の時に念仏相続をふと思ったのです。御影堂や阿弥陀堂の畳と畳の間にひかれている木にたくさんの傷がついているのです。その木を磨いていると、会ったことはない人たちでも、こうして受け継がれてきている念仏の灯があるのだなと感じました。
私にも子供がふたりおります。長男とは一緒に暮らしていませんが、それでも何か伝わっていくものがあるのかもしれないと思いながら、念仏相続について考えさせられていることであります。ありがとうございました。
本多房子 前坊守 (釋尼 芳翠)
おはようございます。私も88歳になりました。あと何回、仏縁に遇わせていただけるのかなと思うこの頃ですが、報恩講をはじめ、法話会などで、ご門徒の皆様とお会いするとことがとてもうれしいことです。
私が坊守をしていたころのご門徒に会うと、昔のことを思い出します。また、前坊守になっても、ご門徒の皆さんが声をかけてくださるので、この年までお育てをいただいてきたことに感慨深いものがあります。年を取り、体の自由が益々きかなくなってきましたが、すべて阿弥陀様の世界の中でのことで、皆ありがたいことだと思います。あとどれぐらい生きられるかなと思ったりもしますが、ご縁を大切にしていきたいと思います。ありがとうございました。
蓮光寺報恩講2022 結願日中法要法話 11月6日(日)
2023年4月7日公開
「人の執心(しゅうしん) 自力のこころ」
追善供養と報恩講
皆さん、岐阜県から参りました林です。どうぞよろしくお願いいたします。
親鸞聖人のご法事を「報恩講」という名前でお勤めしておりますが、皆さんの親族が亡くなったご法事も報恩講であることを忘れてはならないと思います。
ご法事には2つの捉え方があると思うのです。亡くなった方のためにお勤めをするということは、一般的には追善供養と言います。この「追」は、亡くなった方々にこちらから善いことをしてあげると言ったらわかりやすいでしょうか。亡くなった方を弔うということですね。一般的にだいたい仏教で言われますご法事はこうなっているのです。岐阜県では「お経を亡き人にあげる」と言います。このように多くのご門徒方は思っておられます。
私の方では、住職のことを「ごえんさん」と言います。「ごえんさん、親の七回忌だから、お経さん、あげてもらえんやろうか」と言われます。私は「どこへあげるんや。棚にでもあげるんか」と聞くのですけれども。こちらから向こうへ、死者へ手向けるのですが、よほどこちらの手向ける心が清らかでないと、そこに余分な思いが入るのです。心の中には「お経をあげたから、こっちへお返しを」ということがあるのです。追善供養というのは、取引になっていくのです。だから、追善供養の場合は、こちらの心が清らかで純粋でなければできないのです。
聖道門仏教と一般に言われますけれども、比叡山延暦寺とか真言宗高野山は修行したお寺さんが、死者へ手向けるわけです(自力の回向)。
ところが、平生、損や得や、好きや嫌いやと言っている私たちが、死者にあげるというのは、それはどこかに取引の心が入るわけです。例えば「きちんと親のご法事を勤めたのに、何でこんな目に遭わないけないのだ」と、こうなるわけです。
私のお寺に、以前、面白い総代さんがおられたのです。亡くなられて5、6年になるのですが、こうおっしゃったことがございます。「ごえんさん、わしゃ母の法事を勤めるたびに思うんだ。わしが子どものときに、駄賃くれなんだ」と。駄賃って小遣いです。そして「うちの母はけちやったと、法事のたびにそれを思い出すけれども、どうやろう」と言われるから、「それはあんたの心が悪いのや。取引をやっておるからだ」と、こう言ったことがございます。
『歎異抄』の中に「父母の孝養(きょうよう)のために念仏申すことは一度もない」と、親鸞聖人はおっしゃるでしょう。「孝養のため」というのは、追善供養のことなのです。そのための法事を親鸞聖人は勤めないのです。
では、どうするかと言うと、親のご恩というものを知って、それに応える生き方をあらためていただき直す。これが追善供養に対して「報恩講」という意味ですね。だから、報恩講は恩を知るということ、知恩です。これが大事だと。これは親鸞聖人が私たちにお念仏の教えにより伝えてくださったご法事の内実であります。
ですから報恩講は一年に一度お寺で勤めるだけではなく、私たちは常に知恩の心、恩を知る心をいつも忘れますので、思い出させていただく。そして、それに応える生き方を私たちがする。応えるために何が要るかと言うと、自分を見直す眼が要るということです。常に私たちは欲望によって振り回され、損得、好き嫌いの取引の心から逃れることできませんので、自分を見直す眼が大切なのですね。
そして、恩とは恵みという意味があります。何が恵まれるかと言うと、本当の利益、「真実の利」、これは『仏説無量寿経』というお経に「恵むに真実の利をもってせんと欲してなり」と、おしえられています。
では、「真実の利益」とはどういう利益なのか。「仮の利益」また「偽物の利益」それに対して「真の利益」であります。仮(け)というのは仮(かり)にですから、これは日常生活の中で自分の手に入るといいなと思うものが入ること。欠乏したものが手に入ることが仮でしょう。偽物ではない。偽はその利益を得ることによって、自分の人生を駄目にしてしまうようなものを得る。こういうことがあります。今問題になっている某宗教団体は偽の問題ではありませんか。
ですから、報恩講を勤めるということは、私たちは知恩の心、恩を知る心、そしてそれに応える自分の生き方というものをきちんといただいていくことです。こういうことが大事なことであると、親鸞聖人を通していただくわけであります。報恩の行ですね。そのことを伝えるために報恩講が象徴的に儀式として厳修されているわけであります。
それを忘れますと、法事といい、追善供養といい、先祖供養といい、全部一皮めくってみると、取引の心、欲望の心に濁ってしまっています。このことを確認しないと、私たちはうっかりすると、よいことをやっているつもりが、罪(罪福信)になっているのです。こういうことを、まず報恩講ということで考えさせられることでないかなと思うわけです。
親鸞聖人がいただいた南無阿弥陀仏 ─本願の名号─
親鸞聖人は800年前に90年の生涯を生きられた方であります。そして地縁も血縁もない私たちが「門徒」として親鸞聖人からいただいたものは何かと言いますと、ご存じの通り、お念仏の教えです。「本願の名号」です。称名念仏ともいいます。同じ意味です。南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏というのは仏教である限り、多くの宗旨は念仏を申します。何も本願寺だけでの特許ではありません。比叡山延暦寺も念仏がありますし、高野山にも念仏があります。私は台湾へ行ったことがありますが、台湾にも南無阿弥陀仏がございます。仏教である限り念仏があるのです。しかし、南無阿弥陀仏の受け取り方が違うのです。そうすると親鸞聖人が明らかにされたお念仏とは何であろうかということです。
念仏に本願という言葉がついていることが大事でありますね。本願の念仏であると。「本願名号正定業」と、「正信偈」のお勤めをしました。「正定の業」とあります。業は個人的行為を表します。日常生活のなかで、見たり、聞いたり、思ったりするのを「業」と言います。そして、その業はずっと私たちの経験として身に付いてくるものでもあります。これは「宿業」と言います。
今、ここに座っておられても、いろいろなことを考えておられましょう。もしかしたらお昼ですから、心は家に帰っておられる方もあるのではないですか。ここに身はあるけれども、心は家に帰ってしまっている。こういうことはいくらでもありますね。
私たちの心は散り散りに散っているのです。それは何によって散るかと言うと、「縁」による。私がつくるよりも前に、つくらされる条件が与えられるのです。それによって見たら見たもの、聞いたら聞いたもの、思ったら思ったものへ心が散っていくわけです。これを「散心(さんじん)」と言います。これが私たち日常の心なのです。
比叡山延暦寺の千日回峰行をテレビで放映していましたけれども、見られたことはございますね。いのち懸けであります。短刀を持っておられるそうです。そして、自分が挫折するということがあると、それで自分のいのちを絶つ。いのち懸けの行であります。しかし、そういうことができる人は「定心(じょうしん)」です。定心と散心、これは善導大師の教えであります。
そして私たち日常は、この散心です。散るのです。これによって一生懸命やっても、全部散りますから、その散る心を正しく定める。「本願名号正定業」、つまり親鸞聖人からいただいた南無阿弥陀仏は、ご本願のはたらきが私たちに散り散りになる心を定めるのです。
しかし、なかなか定まらんのです。ここは難しいところですね。比叡山では、千日回峰行の他に、籠山(ろうざん)十五年というものがあります。昔は三十年だったそうです。あの比叡山の中に閉じこもって、新聞も見ず、テレビも見ず、一心不乱に修行を十五年間集中して行う。これは籠山行と言います。こういう比叡山には行があるのです。「摩訶止観」(まかしかん)の行という、法華の悟りを開くための行であります。止観行なのです。止観行によって定心を開く。そして振り回されない。これは、ほとんどの人ができない。私もできると思いません。
なぜかと言うと、私達は、縁によって生きているからです。ほとんどの人はご縁によって生きていますから、縁が起こるとそちらへ動いてしまうのです。先ほど言いましたとおり、お昼でございます。あと4分でお昼です。カレーライスの匂いがすると、腹減ったなと縁によって心が動くではないですか。
だから、私たちは、思いで生きているというよりも、縁によって生き、それに思いが振り回されるということがあります。だから、正定業は私たちからは開かれませんから、お念仏の教えが私たちにはたらいてきて、正定にはなれないという自覚を通して正定が起きる。これを「自覚」と言います。何でもできると思ってうぬぼれている私たちに、止まらないだろうと。止まらないということを通して深い慚愧(ざんぎ)の心、頭が下がる心、これが止まったことになるのです。人間は自覚を通して、開かれるわけです。そのお念仏を私たちはいただいているということです。
親鸞聖人のご法事を、報恩講としてお勤めをし、お念仏(本願の名号)をいただいて、自分の人生を正しく定めていく。定まらないなという慚愧の心を通して定まっていくのですね。頭が下がる生き方です。できないなという深い懺悔を通して、心が定まっていく。これが報恩講で本願の名号をいただくということでございます。
親鸞聖人もお念仏の教えをいただかれて、親鸞聖人自身が自分の中に見つけられた、この定まらない心、闇の心を自覚された。何をやっても自分の心が定まらず、自己中心的で、常に自分は正しいとして、人をけなし、下手をすると殺しまで起こしてしまいかねない心を自己の内面に見いだされた。
このことが、今回「人の執心、自力のこころ」をテ-マとしました意味です。これは親鸞聖人自身がそういう自分を深く見つめられて、念仏の教えに出遇うことによって、自覚された内容であります。
このことは「しばらく思慮すべきこと」であると、親鸞聖人がいわれているのであります。私たちは、縁が来たら、常に心が散っていって、自己を失うのです。自分を失った人間ほど面倒なことはございません。ですから、親鸞聖人は深く念仏の教えを自分もいただかれ、散り散りになって自己を失っていくような、この一番根深い問題に目を向けられた。ここが親鸞聖人のすごいところであります。
これは、「本願名号」の本願、即ち、四十八願の第二十願のであります。本願は阿弥陀さまが私たちに願いを立ててくださった。私たちの都合よいことを、仏さまにお願いするのではないのです。
ところが、南無阿弥陀仏も私の思い通りになるためのご祈祷に使われてしまうことがあるのです。
念仏を何かのためにとして念仏をつかうなと蓮如上人はいっておられます。今、本堂で「御俗姓御文」が拝読されました。蓮如上人が書かれた私達へのお手紙であります。親鸞聖人のご生涯が書いてあります。その蓮如上人は、弥陀をたのむのが念仏で、何かを付け足して念仏を使うなと。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、どうぞ家内安全、商売繁盛、無病息災、こういう念仏になってはいけないのです。ところが私たちは、そういう念仏にしやすいのです。
家内安全、商売繁盛、無病息災というのは、うまいこと言ったものですね。家内安全は自分の家が丸く収まればいい。でも、その中実をあまり見ていないのです。むしろ他所が少しごたごたしていると、かえってうちでなくてよかったなと。国もそうでしょう。ウクライナでなくてよかったなと。このようになってしまうでしょう。無病息災は、健康で長生きする。商売繁盛は金がもうかるということです。これが私たちの欲望の中身でしょう。そして、それは一般に当たり前になっているのです。それを念仏に付け足しますと、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、家内安全、商売繁盛、無病息災、ほとんど日本の多くの祭りは、そういう祈りがあります。
私が住んでいる村は900戸ぐらいの村です。大太鼓抱えて踊る祭りがあります。雨ごいです。歌を歌いながらそれに併せて太鼓を打つのです。雨ごいは何かと言うと、豊穣を願うのです。天候がよくてお米がたくさん取れる。飢餓が一番怖いから。だから、雨が降らない干ばつが一番怖いから、雨ごいをするのです。先日、10月2日に済んだところであります。その中身はこちらから神さまにお願いする。神仏にお願いして、私達の思い通りになるようにと。祈りが欲望追求になってしまうのです。こういう問題あるのです。
この人間の欲望というのは、例えば、お金もあり、地位もあり、健康で長生きすることは大事なのですが、問題は健康で長生きして、お金がたまると人間はだいたい濁(にご)るのです。皆さん、だいぶ濁っておるでしょう。私もだいぶ濁っています。
ですから、時々は濁っておるなと、掃除をしないと、どろどろであります。そして、その濁りは何かと。本当のことが見えなくなるということです。濁るというのはそういうことでしょう。それで最後に何が見えなくなるか。自分が見えなくなるのです。金魚を飼っていますとよく分かりますね。金魚の水をかえてやらないと、だんだん濁ってくる。金魚が見えなくなりますね。私たちは、自分はきれいで、自分のことは何でもわかっていて、澄んだ水の中におるような気持ちで見たり、聞いたりしていますけれども、実は欲望という濁りの中にとっぷり漬かって見えていない。人が持っている心の深い闇であります。
親鸞聖人の生涯に学ぶ ─人生の変わり目・転換期─
親鸞聖人の90年の生涯、平安から鎌倉へ武士の時代へと大きく変わる状況の中で、人は、欲望(名利心)追求の歩みが、人間が濁っていくということに気付かれた。それは、現代の経済成長の歩みが、命が見えなくなりすべてを物化(商品化)していく歩みと似ていませんか。
親鸞聖人がどこで生活されたか。居場所というものを通して親鸞聖人の90年の生涯をいただくことができると思うのです。居場所というのは時代と社会であります。
特に、鎌倉時代ですね。今晩、「鎌倉殿の13人」のテレビがあります。見ておられる方も多いと思いますが、どのように見ておられますか。
テレビドラマでは、そろそろ承久(じょうきゅう)の乱が起こります。承久の乱は日本の歴史を大きく転換させた一つのターニングポイントです。天皇、朝廷を中心にした政治体制から武家が力を持ってくる、日本における大きな転換期であります。
その転換期に北条一族が力を持ってくるのです。見ておられる方は北条義時の顔(役者の演技です)を初めから見ておられますか。初めは柔らかくていいでしょう。今どんな顔をしていると思いますか。自分に都合の悪い者は、全部殺していきます。たとえそれが身内であっても。そして、北条執権政治が生き残っていくわけですね。そして、元寇の役という蒙古の戦いにも打ち勝っていく。
義時は、初めは優しくて、本当にいい青年だというところから始まっていくわけです。それが時の流れと自分が置かれた地位、即ち、権力を維持するために思い込んだ正義のために抹殺していきます。権力が強くなれば必ず敵ができます。その敵をいかに抹殺していくかによって、生き残れるわけです。
権力者はだいたい二番目の権力を持った者を殺すのが常套(じょうとう)手段であるようです。義時は一人ひとり殺していきます。たぶん今晩放送されると思いますが、それに敵対するのが後鳥羽上皇です。見ておられない方はすみません。NHKからコマーシャル代をもらっていますもので(笑)。今晩八時から「鎌倉殿の13人」で放送します。全て殺していくのですね。これはすごいことです。
この当時、後鳥羽上皇がその当時、絶対的権力者でした。それが鎌倉幕府、北条執権政治とぶつかります。後鳥羽上皇はどういう方がご存じですか。後鳥羽上皇は法然上人、親鸞聖人を流罪にした人でしょう。そして、法然上人のご門弟4人は打ち首です。2人は鴨川で打ち首、2人は近江へ逃げて打ち首です。流罪となった親鸞聖人は越後(新潟県)へ流されます。そして、法然上人は四国の方へ流されます。土佐へと言われてますけれども、土佐まで行っておられないようです。親鸞聖人は35歳の時です。念仏弾圧(承元の法難)、細かいことは時間がありませんから、あとはご住職に聞いてください。
親鸞聖人は9歳で比叡山に入り、29歳で山を下り、法然上人の門に入り「唯念仏のみ」と目覚められた。そして、比叡山のあらゆる修行を全部捨てられた。捨ててという言葉を「閣きて(さしおきて)」といわれてます。
比叡山が駄目だといわれていません。「さしおきて」というのは、とても私にはできそうにもないと言ったらわかりやすいでしょうか。修業は尊いことかもしれないけれども、私にはご縁のないものと、さしおいて、当時、智慧第一と言われた法然上人に出遇い、そして、本願念仏の教えをいただかれた。親鸞聖人が29歳の時です。
法然上人の京都吉水の教団は、だいたい380人ぐらいだったといわれます。そこで平穏な時を過ごし、法然上人の門弟の中でお念仏の教えをいただいて生活されていました。そこに恵信尼公がいられた。親鸞聖人の奥さまになられる方です。
恵信尼公、これは公家のお嬢さんです。九条兼実という関白に2度までなった方のところにおられます三善(みよし)家のお嬢さんです。その方と親鸞聖人は結婚されるのです。正式な結婚です。
このころは僧には戒律があり、結婚することは女犯(にょぼん)と言いまして破戒になります。僧侶が女性と交わることは戒律を破るということで、無間地獄に落ちるということで戒められておりましたが、法然上人のお勧めもあり結婚されたのだと思います。上人の了解を得て、恵信尼公という方と正式に結婚されます。これも当時の日本の仏教史上初めてでございます。
この恵信尼公が親鸞聖人の奥さまとしてずっと付き添われて、親鸞聖人が35歳のときに念仏弾圧にあっても、共に越後(新潟)の方へ行かれるわけです。お子さまは5人いらっしゃいました。そして、雪の深い越後で生活をされるわけです。
念仏弾圧によって親鸞聖人が越後へ流されて、罪が解かれるのが39歳の時です。そして、42歳になりますと都京都に帰らずに、家族と共に善光寺の方へ向かわれます。親鸞聖人は家を一度も持たれたことがないです。
信州信濃の善光寺の方へ家族ごと移られるのです。親鸞聖人は京都、そして流罪で越後、流罪が解かれて、そして関東へと移られるのです。62歳のころ、関東から京都へ移られ、90歳で入滅されます。この4つの場所の中で特に流罪地である越後、そして関東での生活が親鸞聖人の大きな変わり目だと思うのです。
親鸞聖人のご生涯のご苦労により、「本願念仏の教え」を私たちがいただくことができた。そのご恩徳に報いる。私達もやはり自分の一生涯に変わり目がある。その変わり目をどう生きていくかということが、聖人のご生涯の歩みの中に大切な視座があると思うのです。
越後に流罪になったときに、親鸞聖人にはお弟子はほとんどありません。罪人として流されますけれども、奥さま恵信尼公のご関係の荘園がありますから、そんなに貧しいことはありません。やはり貴族出身の比叡山で修行されたお坊さん(官僧)が来られるということで、越後の人たちも、一目置かれていたのでないでしょうか。
しかし、そこで親鸞聖人は弟子一人も持っておられません。厳密には1人だけおられたと聞いていますが、ほとんどないわけです。先輩の中には、沈黙の時代と言われる方もおられます。
越後におられたときに、親鸞聖人はお弟子を持っておられないということは、ひたすら学ばれたのだと思います。当然流罪というのは、ある程度豊かであったといえども、やはり自分で田地田畑を耕したり、生活のために何かをしなければなりません。お子さま連れですからね。衣食住に振り回されて、仏法なんて言っておられないぐらい振り回されることもあったのでないでしょうか。生き方など考えている余裕がないぐらい、食べていくことに対して大変なこともあったと思います。周りにおられる人々もそのような方が多く、しかし、愚痴も言わずに、その日、その日を生きておられる。その人たちと交わって、人間を学ばれたのではないかと思います。その人たちは、どのような救いを求めておられるのか、どういう教えをいただこうとしておられるかということを、ひたすら学ばれたと思います。罪が解かれてすぐに関東へ移らずに2年間越後におられたということは、そういう交わりがあったということだと思います。法然上人の念仏の教えが、越後の人たちによって親鸞聖人の上に深く開花したのだと思います。今、私たちは何をしなければならないかということを、そこで学ぶことができるのです。人間を学ぶというのは、人間の外じゃない。人間そのもの、内なる心を学ばれたのだと思います。
真宗という名は、親鸞聖人から始まったとは限りません。仏教そのものを真宗と言う歴史もあります。それを「外道に対して、仏教を真宗」と言うのです。これは私が教えていただいた先生からお聞きした言葉です。仏教以外のものを外道と押さえたのは、外ばかりに気が向くということです。客観性のみに力を置きます。
皆さん、あそこは本堂の「内陣」と言いますね。皆さんのおうちは「お内仏」と言います。外に対して内、内陣、仏さまの世界は、本堂ではお内陣、皆さんのところにありますお仏壇はお内仏と言うのです。それは外ばかり向いている私たちに内を向けと。内心ですね。自己を見つめよと。自分を欲望によって、いつの間にか私の意識が、外へ向くようになっています。だから、自己に帰れと。
仏教は外道に対するものです。私たちの生き方を見直す。その仏教を使って、どうぞお金がもうかりますように、長生きできますように、健康でというようなことを付け足したら、やはりおかしなことでしょ。
時代と環境の外道性
外道は、時代と環境という2つの面があります。時代ということで考えますならば、高度経済成長の流れに乗り、お金を持つ豊かさ(所有)を追い求める。しかし、そこには、資本主義社会が持っている闇もあります。資本主義が悪いわけではないのです。しかし、資本主義社会は簡単に言いますと、資本により商品をつくって売って、金をもうけて豊かになっていく。そのためにも欲望がないと、資本主義社会は成り立ちません。だから、欲望をどんどんと膨らませていくわけです。その欲望を膨らませるために、自分の思いでなしに、コマーシャルによってたきつけられていくわけです。私たちはいつの間にか、欲望満足のためにマインドコントロールにかかっているわけです。テレビ、スマホでも、この商品を買わないと損ですというコマーシャルがずいぶんありますね。これは必要か、必要でないかを決めるのは本当は自分なのです。しかし、特に、最近は情報量が多く自分に決められず、コマーシャルによって踊らされている。環境が、経済中心の市場になり、自分を見失っていく、そういう闇を持っているのです。
コロナ前まで欲望全開の状況で、そこで何が起こったかというと、人間関係が崩れてきたのです。コロナが始まる前は、殺人事件の親族殺人が50%を超えていました。もはや日本は高度経済成長によってプラチナ社会になったと、こう言われたものです。経済産業省の方の話ですが、そのプラチナ社会の中で何が問題かというと、福祉の問題が残る。福祉というのは、お互いが助け合う場をつくっていくという、そういうものが福祉なのです。それが崩れてしまうと、せっかくのプラチナ社会と言われる高度経済社会というものが根こそぎ駄目になる可能性があるということを、統計を持ってきてくださってお話しされたのを聞いたことがあります。その豊かな商品社会で起こったことが、お墓が捨てられる。お骨がさまよう、葬儀が直葬。そして、親族殺人が増えている。ものすごく豊かな、金さえあれば何でもできる社会におこっていることなのです。人まで買えるのです。人を商品化(物化)する、心は買えませんけども? 労働賃金というかたちで、実は下手をすると商品にされてしまいます。これがどんどんと広がってくるのです。
そして今年、3カ月くらい前でしたか、テレビである評論家の方が「もはや日本は殺人事件の親族殺人が60%を超えた」と言われました。人間が崩壊していっているわけです。
人間とは何かが問われているのです。人と人との関係が崩壊し、そして孤独社会を生み出してきている。この孤独ということが、仏教でいうと地獄ということです。地獄の一番深い地獄は、言葉が通じないということです。言語の往来がない。人と人とが出会っても感動がない。
年を取ると、一日一日が早く過ぎるのを感じるのは、感動がなくなっているからだそうです。これは、「チコちゃんに叱られる!」で放送されていました。「何で一日一日が、こんなに早く過ぎるの」とチコちゃんが問う、その答えが、感動を失ってきているからだそうです。そういえばそうだなと。年を取っていくと、話すことは、病気と病院と薬の話ばかり。本当に、真に話す者もない。家族全員、たまにそろっていても、若い人の話が半分わからない。また、わかったつもりで「えへへ」と笑っている。そういう家族のかたち。皆さんのところは、いかがお過ごしでございましょうか。
私は今一人で生活しています。去年、妻を亡くしましたので。子どもたちも、孫も全部、神奈川に住んでおります。息子は大学に勤めておりますので、神奈川。嫁も大学に勤めております。ご門徒が「ごえんさん。早く帰らせんと、帰ってこうへんぞ」と言われました。私は今日、ここに来るまでに、洗濯物をちゃんとたたんで、夕べの片付けをし、そして、朝は早く済むようにおかゆをつくって、それを食べて、急いできたのです。1年になります。愚痴を言ったら、きりがありません。しかし、引き受けてやってみると面白いこともあります。女性は、よくこれだけのことを日々こなしておられるなと感心いたします。妻が生きているうちに言ってあげればよかったと思いまして、ありがとうと。一言も言ったことがなかった。皆さん、ぜひ、言ってください。
現代と鎌倉時代は同じではないですが、親鸞聖人が越後におられたときは、やはり衣食住の生活の中で家族を抱えての環境でなかったかと思われます。京都法然上人のところでは、法然上人のご門弟がおられる一つの組織ですね。兄弟弟子も、先生も、みんなそろっているのです。ある意味では分担されているわけです。越後は、そうはいきません。日常生活というものは、そういうものではないですか。
日常生活の散り散りの心に振り回されて生きるしか仕方ない。ゆっくり仏法の勉強なんかしている暇もない。それを、ひたすらそこに身を置いて学ばれた。それも流罪地であります。栄転して行ったわけではありません。そういう親鸞聖人の35歳からの流罪地での生き方の中から、私が学ばねばならないのは、今、本当に思い通りにならないことばかりです。下手に思い通りになるとひっくり返ります。だから、与えられたものの中で、思い通りにならないものをきちんと受け取って、そこに自分の喜びを見つけていく。創造性と感覚が大事だと思います。
創造性というのは、できることなら、やってみようという、そういう創造性。それと今まで気付かなかったものに感ずる心です。念仏の教えは、感の教えです。感動の「感」です。感ずる。だから念仏の教えを聞くということは、感覚が、鋭いとは言いませんけれども、今までにない感覚が呼び覚まされてくる。こういうことが大事だと思います。
何をよりどころとして生きるのか、どこに向かって生きるのか
親鸞聖人は、越後で弟子を持とうと思っておられたのではないと思います。生活を共にしながら、その土地の人と苦労を共にしながら生きておられ、そして、流罪が解かれ、子どもと女房を連れて、信州信濃の善光寺の方へ足を運ばれた。
ここで、悲しいことと出会われるのです。縁というものは不思議なものですね。干ばつに出会うのです。越後から歩いて行きますと、佐貫(群馬県)というところを通ります。ここを通って善光寺の方へ行こうとされたのです。その途中の佐貫というところを通られた時大飢饉に出会われます。ひどい干ばつに会われます。長く雨が降らないということです。雨が降らないということは、大変怖いことなのです。作物が取れません。米、麦、全部取れません。そうすると、そこで起こるのは、人が餓死していくのです。娘が売られ、食うものがないから餓死していくのです。それに伴って必ず起こるのが、はやり病(やまい)です。多くの方が亡くなっていきます。コロナとちょっと重ねてみてください。
親鸞聖人は、それを見てどうされたか。思わず、祈りをされたと思います。人は、何ともならないとき祈るしかありません。祈りのない宗教はありません。全てに祈りがあります。代表的なものは、イスラム、キリスト教。みんな、祈りです。神に祈る。仏教も、初めは祈ります。そして祈って、その祈りを通して、人間の心はよいことをしたい。何かをしてあげたいというこころが起こるではないですか、自分が健康ならば。人を助けたい。利他の精神です。他を助けてあげたいというこころが起こるでしょう。
そうしたら、どうしたらその人たちを助けることができるか、慰めることができるかということになって、そこから祈祷というものが起こります。ご祈祷です。親鸞聖人は、これに迷われるのです。比叡山で法然上人に出遇ったとき、これは捨てたはずなのです。「ただ念仏のみ」と決定したにもかかわらず、思わず多くの人々の苦しみを見て、祈り、祈祷をしようとされるのです。
どのようにされたかと推測しますと、親鸞聖人が比叡山におられた時された行、常行三昧だと思います。常行三昧での修行は、お堂の中でお経を読みながら歩き、自己の悟りと国土の人民のために祈るのだと思います。その経験が三部経を千回お経を読んで、人々を慰めようとすることを思い出し祈ろうと思い「これはどうしたことか」と迷いに気づかれた。
私の勝手な推測ですけれども、親鸞聖人は迷われたと思うのです。縁が来ると、人は善によって迷うということがあるのです。善なる心。よき心。人々を助け、何とかしてあげたいという心。それが迷いとなって起こるわけです。
よいことと思ってしてますから、迷いと思いません。聖人は、人々にお経を読み苦しみから解放し慰める、比叡山の時のことが浮かんだのだと思います。比叡山では、これを遮那(しゃな)行といいます。ご祈祷がされるわけです。比叡山のご祈祷の代表的なものは護摩壇を焚くということです。止観行に対して、遮那行です。
そして、三部経を千部読誦して人々を慰めようと思って、はっと気付かれるのです。人は迷う存在なのです。何に迷うかといったら、現況に対してどうするのかということです。その根底に生き方、「何をよりどころに生きるのか。自分の人生は、どこに向かって生きるのか」が問われているのです。これを「帰依」といいます。
何をよりどころにするかということは、あらゆる行為を何によって決めているかということです。間違うこと、また上手くいった時、それを立ち止まって自己点検する、何をよりどころにそれを決めたかを確認することができているかどうか。人生のよりどころ、それと人生の目的、即ちどうなろうとしているのかです。
皆さんは、何をよりどころに決めておられますか。自分の思いではないですか。その思いは、どういう基準で決めていますか。金と健康さえあればという基準ではありませんか。そろそろ皆さんの中には、お金を置いていかなければならない、持っては行けないからという方もおられるではないでしょうか。この財産を誰に渡そうかと思って、悩み、また、お座敷の床を剥がして、そこにつぼを埋めてありませんか。国税局が入りますよ(笑)。
よりどころというのは、時代によって変わります。今は完全に経済中心の社会ですから、貨幣というものが全ての基準になっていくと言って間違いないと思います。シェークスピアは「貨幣が神のごとくはらたく」と言った。シェークスピアのときから、もう始まっているのです。日本は今、そのとおりです。
今日も皆さん、報恩講にお参りしていただいていますが、もうかることがあったら、ここへ誰も来ません。それほど社会というものが、経済中心の構造で成り立っているのです。そのような環境によって、私たちの心は振り回されているわけです。
今、カルト宗教が3千ぐらいあるといわれます。そして、若い人たちが多く入っていると言われます。「お寺さん、ぼうっとしていたらいけないよ」と言われました。25歳の孫と話しておりましたら、また面白いことを言うのです。「何か私を左右するような大きな神さまが、上にずっと上がっていって私を見ている」と。「どこで見たのだ」と言ったら、スマホです。
宗教の勉強なんか、何もしていません。だから、ちょっと思い通りにならない不思議なことが起こると、祈りから祈祷へということになるのです。さらに情報が多いものですから、常にそれに操られるのです。スマホは、使いようによってものすごく便利ですが、危険な面があることを忘れてはなりません。
今年の5月に私は胃がんで入院しました、早期発見でした。時々検査をされることは大事だと感じました。それでなかったら、今、わたしはここにおりません、私は。早期発見で、内視鏡で取れましたから、どうもありませんでした。でも、1週間、病院に閉じ込められました。コロナ禍ですから歩いたらいけない。ペットボトルを買いに行く時だけです。時々、看護士さんが来てくださる。これはありがたかったです。もう妻もおりませんでしたから、私一人でじっとしていました。テレビなんか、まったく面白くない。人が胃を治療してもらって入っているのに、テレビの中はビフテキを食べている。腹が立ちます。何にもすることがない。
唯一あったのがスマホです。これはひとりぼっちになっても対話ができるのです。映像を通してもできるのです。皆さんも、スマホをお使いでしょう。対話ができますし、出会えますし。ひとりぼっちでも、牢屋に入れられていても。これは便利だなと思いました。
ただし、この便利なものが、使い方によっては、先ほどのカルト宗教ではありませんけれども、おかしな情報も入っていて、人を操るものにもなります。スマホが悪いのではありません。スマホを使う人間の問題です。人間が問われているのです。
人間というのは何か。あなたは、何をよりどころに生きているのか。あなたの人生はどちらに向かって生きているのか。死に向かうならば、今、楽しまないと損だと思って、毎日、ご馳走を食べに行ってコロッと逝くという。コロッと逝けばいいですけどね。そうはいきません。
人の執心、自力のこころ ─自力の心は正義の自己主張─
親鸞聖人は越後に流罪になり、そして越後の罪人としての在り方から解放されて、関東に移られる途中、佐貫というところで苦悩の多くの人々に出会い、賜った「念仏の信心」をより深められた。そのことは、現代の私たちの状況とも重ねて考えることができると思います。
即ち、親鸞聖人は関東に行かれる途中、苦悩の人々との出会いをご縁に、その人たちを救いたいとお経を千部読み初めて、人の迷いの深さに気がつかれ経を読むのを止められた。そして関東に移られ、多くのご門弟ができます。だいたい1万人を超えたといわれます。越後では、門弟はないのです。それが、この佐貫を通り、多くの人々の苦しみに出会い、なんとかその人々を苦しみから助け慰めたい(衆生利益)と「三部経」を千部読み始めようとされ、これはどうしたことか「名号(念仏)」のほかに何の不足あって経を読もうとしたのかと思い返して経を読むことを止められた。その迷により「人の執心、自力のこころはよくよく思慮するべき」だと言われた。聖人42歳の時です。このことを奥さま恵信尼公に語られたのが、59歳のときです。
「人の執心、自力のこころ」このこころが念仏ひとつと決定したはずだが、深い悲しみに出遇うことによって、祈りから祈祷へという動きになって迷った。それを生み出した「人の執心、自力のこころ」の迷いの深さに気付かれたのです。
「人の執心」は執着心から離れられないということです。人は、どんな状況になっても、執着心から離れることはできない。頭がよければ、頭がいいという執着心が起こるのです。面倒でしょう。善を行えば、俺はよいことをやっているという執着心が起こる。そして、それを縁として、外を批判するのです。
だから現代でいうと、一番力のあるものは権力と財力ですから、権力と財力を手に入れて上がろうとする、そうすると執着心も強くなる。その執着心は、どういう執着心かというと、「自力の心」です。自力というのは、「われはよし」とする心です。自分の思いは正しい。これがよいことなのだと思い込むことそれに執着するのです。それだから親鸞聖人は、「自力の執心」とおっしゃるわけです。
人間は、どのような状況になっても、自力の執心は消えないのです。この自力の執心は、私は正しい、私は正義だと思い込むと消えないのです。だから、人間は助からない存在なのです。人間の力では、人間が助からないのです。
それに対して他力教えがあります。他力は本願力といいます。仏さまは、このように教えを説かれたのです。人間は、人間では何ともならない、助からないような人間が、実は素晴らしいものを持っている。それを見失ってしまっている。その見失わせた深い在り方が自力の執心。われはよしという執心である。
ここでは、あまり感じないかもしれませんけれども、家に帰るとすぐにわかります。自分に都合のいいことを言ってくれる人は、みんないい人ばかりです。自分の思いに反対する人は、力が、自分がそれよりも上だったら、上から言います。自分の力が下だったら、黙ってじっとしているのです。だいたい、皆さんの年だと黙ってじっとしている。今に見ていろと。そういうことが身内を殺していく、親族殺人が増えているということの元でもあるのです。
そして今、過疎がどんどん増えていって、家族が、心の行き違よりも、社会の生活状況が、人と人とが出会えない。家族がばらばらになっていくような状況がきております。若い人たちは、海外への転勤も増え、ベトナム、インドの方へと行かれると思います。そうすると、もはや家族がみんな、親子、夫婦、兄弟(姉妹)、じいちゃん、ばあちゃん、そろってという家族構成で生きるのは、ほとんど不可能に近くなるのでないでしょうか。
私の家族は、少し前までは、母も健在のときには、6人の家族でした。今、息子夫婦は神奈川にいまして、私一人で生活しています。今、蓮光寺さんに来ておりますので、私の寺は誰もおりません。セコムが留守番をしております。お寺がそんなことをやらないといけないのは、情けないです。寺は、いつでも誰でも拝める場所にしておかなければいけない。しかし、いつも本堂に入れるようにしておくと、今度は泥棒にやられます。もう2回、賽銭泥棒にやられました。
だから、自分の生き方は正しい。思いは間違いないと思って、それを通そうとすればするほど、地獄、即ち、孤独になっていきます。
地獄とは、ひとつは「人間の音響(おんごん)なし。」響き合わない。皆さん、人と出会って響きますか。「いやあ、久しぶりやなあ」というのは、めったにないでしょう。出会わないのですからね。2つ目は「言語の往来がない。」一番深い地獄です。言葉が通じない。そして、「われ、今、帰るところなし、孤独にして同伴なし」です。帰るところがない。今日は皆さん、ここに座っているのは、帰るところがあるからです。しかし、仮の帰るところです。人生、どこへ帰りますか。まさか、棺の中ではないでしょうね。
棺も上中下があります。みんな、お金がかかるのです。彫刻が素晴らしいのは上。布を貼ってあるのは中。何もない木の白い肌は下。嫌になってしまいます。
こういう状況を生み出してしまった豊かさの中の闇。その闇の一番深いのは、「われはよし」とする執着心です。これを現代的に言いますと、自力の心とは、「我が思いの絶対化」「正義の自己主張」と言ったらどうでしょうか。正義の自己主張。私は正しいことをやっているという主張です。やっかいですね。悪を生み出す善。
よいことをやっていることが、実は悪であることがあるのです。よいと思っているのですから気がつきません。そういうことが起こるのです。だから「やってやったのに」「助けてやったのに」「手伝ってやったのに」と、「やった」が付くのです、私の地方では、やったを「やったった」と言うのです。そして、思い通りにならないとぷつんと切れるのです。身近なものほど切れやすい。なぜかというと、要求する度合いが強いからです。
親鸞聖人は、深い自覚を通して、関東へ行かれます。初めに善光寺の方へ行かれます。そして、高田門徒という教団ができます。この高田門徒が後に三重県に移ったのが、高田の専修寺。高田派の本山であります。関東に高田門徒、鹿島門徒、横曽根門徒等の門徒集団ができ、一万人を越えていただろうといわれます。
聖人のご生涯から、現代の多くの問題を持っている私達は、学ぶチャンスを生きているのでないでしょうか。親鸞聖人ほどのことはできませんけれども、もう一度、高度経済成長の中で、私たちはいつの間にか「我」が強くなって、執着心が強くなり、ちょっと豊かになると「私の言うことを聞け、聞かないやつは仲間に入れない」と。
こういう心は直りません。何をしても直らないのです。人間は、それほど深い闇を持っているのです。これを「無明」といいます。
親鸞聖人は、ただ無明というよりも、「無明の闇」と言われます。無明は暗いにもかかわらず、そこへ闇をつける。「念仏は無義をもて義とす、不可称不可説不可思議のゆえに」と『歎異抄』にあります。「無義の義」は、私たちが払っても払っても出てくる、私のはからいなのです。執着心を持ったはからいです。
その無明の闇を念仏の教えで照す。それが本願念仏の教えなのです。だから念仏は、私を照らして、人間の深い闇を知らせることを通して目覚めさせるのです。救われがたき無明の闇を持っているという自覚により、私たちを支えてくださるのです。
そのはたらきにより私たちは、臨終の一念まで救われ続けていく、気づかせていただくのです。救われてしまったら終わりなのです。そこにあぐらをかきますからね。わかったこととして、あぐらをかくのです。それは歩みを止めることになるのです。菩薩の死といわれています。
救われない者としての自覚をいただき救われ続けていく。念仏の教えに、私たちの闇が照らされ、目覚めをいただくのです。自覚です。これを大乗菩薩道といいます。いつでも、どこでも、誰でもができるからです。なぜかというと、みんな闇を持っているからです。持っているから気付くのです。そこに大乗菩薩道。大乗、全てのものが菩薩道。自分の人生を求め続けていくという力を賜る。これが本願念仏のはたらきなのです。
少し時間がオーバーしてすみませんでした。もう皆さまとは、これで会えないと思っております。一期一会です。81歳ですからね。100歳まで生きるつもりでいても、80歳を過ぎると、一回一回が最後だなと思います。だから、年を取るということは、そういう感動が起こるのですね。
何でもないことでも、これが最後だなと思うと、よし一回きちんと向き合ってみようと思うでしょう。こういうことが、また一つ、大事なことでないかなと思うのであります。
親鸞聖人が42歳のとき、「人の執心、自力のこころ よくよく思慮すべき」だと。奥さまの恵信尼公に言われた教えを、孤独になり、地獄をつくり続けいる私たちがいただかねばならない大事なことであると思うのであります。
自分の生活の中で実験をしていただくと、よくわかると思います。お帰りになったら、すぐに実験できます。例えば、むかっと腹が立って。「これ、やっておいてと言ったのに」と、すぐこうです。このようなことも、お伝えして終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
番外編
報恩講が無事円成し、林先生と住職・門徒が亀有の町を歩いていると、亀有公園派出所の両さんが、私たちに声をかけてきて、お友達になりました。林先生は突然の珍客に大喜びでした。