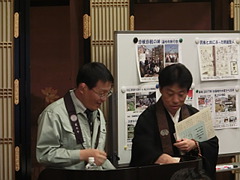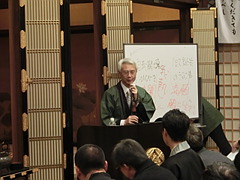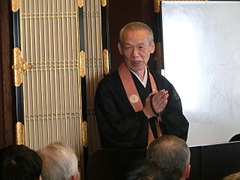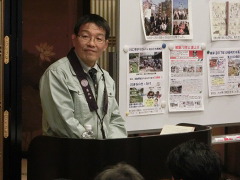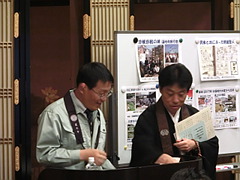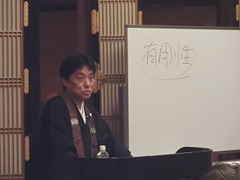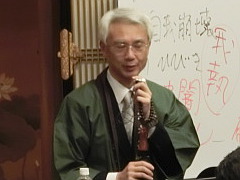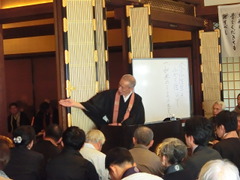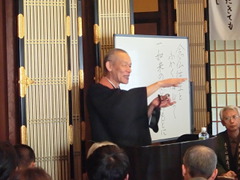報恩講 2016
2016年10月7日公開
11月2日(水)
大逮夜法要 | 午後3時〜5時
- 法話: 橋口茂さん(蓮光寺門徒) 「真宗の教えと私 ─自分の考えとまったくちがった形で救いの道をいただく─」
-
 どうにもならない苦悩の中で、蓮光寺にはじめて訪れてから17年が経ちました。いま、日々の暮らしで、ふっと、愚かな私なのにお念仏申してるのは何でだろう、と思い、とても不思議で、有り難いなぁと感じています。このたび本多ご住職より「君が真宗に出遇ったきっかけや、いま何を感じているかを話してもらえたら」と、貴重なご縁をいただきました。その後Uターンした長崎での近況などを含めて、真宗の教えとの出遇いと私が救われつつある歩みについてお話しながら、親鸞聖人の教えをごいっしょに考えたいと思います。
どうにもならない苦悩の中で、蓮光寺にはじめて訪れてから17年が経ちました。いま、日々の暮らしで、ふっと、愚かな私なのにお念仏申してるのは何でだろう、と思い、とても不思議で、有り難いなぁと感じています。このたび本多ご住職より「君が真宗に出遇ったきっかけや、いま何を感じているかを話してもらえたら」と、貴重なご縁をいただきました。その後Uターンした長崎での近況などを含めて、真宗の教えとの出遇いと私が救われつつある歩みについてお話しながら、親鸞聖人の教えをごいっしょに考えたいと思います。
- 法話: 蓮光寺住職 「教えの眼から人生を見直す」
-
 橋口さんは企業の合理的経営の中で苦しみ、どうにもならないなかで蓮光寺の門をくぐりました。長崎の実家が浄土真宗だったことが、こうして蓮光寺の門徒となる縁となり、人生を大きく転換していきます。教えを聞けば、苦しみから解放されると信じて聞法を続けてきましたが、ある日、「汝、凡夫よ」という如来(教え)からの呼びかけに頷かされ、苦しみはなくならなくても生きていける道があることに気付かされていきます。もっと言えば、苦悩することが生きていることなのだという積極性が芽生えてきたのです。如来の眼から人生を見直すと、「凡夫とは私のことであった」という自覚とともに、生きる意欲があたえられます。そのことをごいっしょにいただいていきたいと思います。
橋口さんは企業の合理的経営の中で苦しみ、どうにもならないなかで蓮光寺の門をくぐりました。長崎の実家が浄土真宗だったことが、こうして蓮光寺の門徒となる縁となり、人生を大きく転換していきます。教えを聞けば、苦しみから解放されると信じて聞法を続けてきましたが、ある日、「汝、凡夫よ」という如来(教え)からの呼びかけに頷かされ、苦しみはなくならなくても生きていける道があることに気付かされていきます。もっと言えば、苦悩することが生きていることなのだという積極性が芽生えてきたのです。如来の眼から人生を見直すと、「凡夫とは私のことであった」という自覚とともに、生きる意欲があたえられます。そのことをごいっしょにいただいていきたいと思います。
報恩講の夕べ | 午後5時30分〜6時30分
- トーク&コンサート: 鈴木君代さん(真宗大谷派僧侶)
-
 【人間はとてつもなく弱いものです】このことは仏さまの教えに遇わせていただいて頷くことができるようになったことですが、今まさに弱い自分を知らされています。 あなたにあいたいと願って歌います。
【人間はとてつもなく弱いものです】このことは仏さまの教えに遇わせていただいて頷くことができるようになったことですが、今まさに弱い自分を知らされています。 あなたにあいたいと願って歌います。
11月3日(木・祝)
晨朝法要 | 午前8時〜9時
- 感話: 門徒2名
日中法要〈御満座〉 | 午前11時〜午後1時
- 感話: 櫻橋淳さん(蓮光寺門徒) 「真宗の教えとの出遇い」
-
 キリスト教徒であった私が、どうして真宗門徒になったか、真宗の教えについて感じたことをお話します。
キリスト教徒であった私が、どうして真宗門徒になったか、真宗の教えについて感じたことをお話します。
- 法話: 狐野秀存先生(京都大谷専修学院長) 「念仏往生とふかく信じて」
-
 正しい三世観があります。みんな〈アミダさん〉の願いを身に受けて、今生に生まれてきたのです。私どもに与えられたいのちが「ナムアミダブツ」と叫んでいるのです。現代は悪しき現世至上主義が私どもの心を虫食んでいるように見受けられます。「今さえ、おもしろおかしく過ごせればいいではないか。後は野となれ山となれ。」いのちの願いを見出せない悲鳴だと思います。親鸞聖人は、そのような未来を見失った私どものために、「念仏往生とふかく信じて」と呼びかけておられるのです。
正しい三世観があります。みんな〈アミダさん〉の願いを身に受けて、今生に生まれてきたのです。私どもに与えられたいのちが「ナムアミダブツ」と叫んでいるのです。現代は悪しき現世至上主義が私どもの心を虫食んでいるように見受けられます。「今さえ、おもしろおかしく過ごせればいいではないか。後は野となれ山となれ。」いのちの願いを見出せない悲鳴だと思います。親鸞聖人は、そのような未来を見失った私どものために、「念仏往生とふかく信じて」と呼びかけておられるのです。
報恩講お待ち受け清掃奉仕
2016年11月1日公開
11月2日(水)から3日(木)にかけて勤められる報恩講に向けて、10月29日(土)、お待ち受け清掃奉仕が行われ、20名以上のご門徒が参加されました。雨の予報で心配されましたが降ることもなく、参加されたご門徒は安心して精一杯掃除に励んでくださいました。
きれいになった本堂でのすがすがしい勤行が勤まった後、田口弘さんが感話され、清掃奉仕のこころについて語ってくださいました。
いよいよ報恩講が始まります。
茶話会
 勤行後の感話
勤行後の感話

報恩講写真特集
2016年11月6日公開
11月2日(水)〜3日(木)、報恩講が厳修されました。2日は曇りで肌寒く感じましたが、3日は快晴となり、気温も20℃を越えて、さわやかな報恩講になりました。日中法要(御満座)は約150名の参詣があり、本堂に入りきれない状況でした。
2日の大逮夜法要では、「真宗の教えと私 ―自分の考えとまったくちがった形で救いの道をいただく―」と題して蓮光寺門徒の橋口茂さんが法話、続いて橋口さんの法話を受けて蓮光寺住職が「教えの眼から人生を見直す」と題して法話。その後の「報恩講の夕べ」では、大谷派僧侶でシンガーソングライターの鈴木君代さんのコンサートがありました。
3日の晨朝法要では、本山で帰敬式を受けた法友を代表して、橋口茂さんと谷口裕さんが感話。日中法要では、真宗門徒となった櫻橋淳さんが「真宗の教えとの出遇い」について感話。そして「念仏往生とふかく信じて」と題して、京都大谷専修学院長の狐野秀存先生よりご法話をいただきました。法話は後日アップしますが、まずは写真でお楽しみください。
大逮夜法要「法話」
2017年1月5日公開
法話: 橋口茂さん(蓮光寺門徒、釋草純、51歳)
「真宗の教えと私 ─自分の考えとまったくちがった形で救いの道をいただく─」
みなさん、こんにちは。橋口茂と申します。私の法名は、釈草純、ニックネームは、はっし〜と申します。今日は、長崎からまいりました。
私は土木技術者として働いており、サラリーマン歴は間もなく30年となります。家族は妻と娘2人の4人家族で、現在51歳です。
かつて、どうにもならない苦悩を抱えて、蓮光寺をはじめて訪れてから17年余りが経ちました。このたび、本多ご住職より「君が真宗に出遇ったきっかけや、いま何を感じているかを話してもらえたら」ということで、「真宗の教えと私 ─自分の考えとまったくちがった形で救いの道をいただく─」というタイトルと、貴重なご縁をいただきました。
今日は、その後Uターンした長崎での近況などを含めて、真宗の教えとの出遇いと、救われつつあるのかわかりませんが、私の歩みについてお話しながら、親鸞聖人の教えをごいっしょに考えていければと思います。
いま、日々の暮らしで、ふっと、愚かな私なのにお念仏申してるのは何でだろう、と実に不思議で、有り難いなぁと感じています。実は、これが今日のまとめです (^^)
せっかくのご縁をいただき、日本の西の端の長崎から参りましたので、つたないお話となり、聞きいただくのはたいへん恐縮ですが、どうぞ、宜しくお願いいたします。
真宗に出遇ったきっかけ 厳しい現実のはざまで
私が真宗に出遇ったきっかけは、仕事で厳しい現実に直面し、過労で燃えつきて、回復する過程で、自分自身に何か問題がある気がして、わらにもすがるような思いで蓮光寺にたどり着いたことでした。その経過を、少しお話ししたいと思います。
私は、高校を卒業して故郷の長崎を離れ、京都で4年間の大学生活を送ったあと、1987年4月に大手の技術コンサルタント会社に入社し、公共事業に関わる調査、設計、技術開発などの仕事に携わりました。
入社して間もなく担当した仕事で、都市化によって身近な自然が失われ、人々との関わりも希薄になり、汚濁したりゴミが投棄されて荒廃した各地の川や道路などの現場をたくさん見ることになりました。こうした現実を目の当たりにして、問題の根底には、効率性を追求する大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会経済システムや、私たちの日常生活、私たち一人ひとりのあり方があるのではないか、と感じました。何とかしなくてはいけない、これが自分の使命なんだと、すごくやる気をもって頑張って働いていました。しかし、入社8年目くらいから、職場の中核的な立場となるにつれて、私は仕事の中で厳しい状況に陥っていきました。
私はいま、サラリーマンが組織の中で働く上では、2つのポイントがあると思っています。1つは、組織が目標の達成を求めるという側面、もう1つは、組織や職場における人の問題があるということです。当時、私は水質が汚濁した川や湖沼、お城の堀の浄化対策などの仕事を担当していましたが、このころ仕事の受注量の増加に合わせて職場の人数も増やしており、私は数人のメンバーの主任として仕事を行うことが求められました。しかし、不十分な組織体制や意志の不統一、求められる仕事の水準の高さとメンバーの力量不足とのギャップなど、様々な問題に直面しました。仕事の配分などをめぐり、職場の人間関係も大きな負担になりました。当時の私には、こうしたことに対処するだけの経験や能力も大きく不足し、トラブルの対処や様々な問題の解決ができずに、仕事が停滞し、悪循環の中で、過労や悩みが深まっていったのです。
さらに私は、技術者としての倫理の問題にも苦悩しました。当時、建設大臣までが逮捕されたゼネコン汚職事件が起きた直後で、土木の分野でも倫理の問題が問われるようになっていました。
私が取り組んでいた川などの水質汚濁の場合には、流域に暮らす地域住民や事業者の方々が排出した汚れた水が主たる原因となります。しかし、公共事業は、どうしてもハード中心の対症療法になる面があるんですね。本当は、地域住民の方々に呼びかけてソフト的に解決することも多くあると思います。しかし、現実はそうはいかず、浄化施設の設置などハードが先行して、ソフト対策は後回し。そうした中で、自分の中に葛藤が出てくる。求められる倫理と現実のはざまで、無力感とか罪悪感が次第に大きくなってつらくなっていったんですね。倫理というものが、私たちを縛っていく、束縛するということがあるんだと思います。
こうした状況でも、成果さえ出れば、大きな充実感や喜びがある。しかし悩みの方が大きくなれば、「俺って何やってるんだろう」と思うようになる。余りにも忙しすぎて大事なことがだんだん見えなくなって、職場でも家庭でも配慮に欠けてしまって、人間関係がぎくしゃくする等の悲しい状況が、たくさん出てきました。
私が過労の状態に陥ったのは、自分なりにやる気を持って頑張ったことで仕事が増えて、無力感に陥り始める。だけど、「まだ頑張れる」と思いながら長時間労働を何年も続けているうちに、絶望的なつらさや空しさ、空虚感をかかえながら、慢性的に疲れ切っていったわけです。
過労で燃え尽きて
1997年の9月のはじめ頃でした。私は、当時暮らしていた松戸市の馬橋駅から、いつも通勤で使っております千代田線に乗ったのですが、どうしても会社にいけなくなり、途中の町屋駅で降りて、松戸方面へ戻ってしまいました。非常に気分が重く、何かおかしいと思いまして、その足で松戸駅前の精神科のクリニックに行きましたところ、軽いうつ状態との診断を受けました。このころ、長女はまだ1歳半で、次女が生まれる3ヶ月ほど前のことでした。
その年は会社を1週間ほど休んで、半年ほどクリニックに通って回復したと思っていました。しかし、その後も多くの仕事を抱えて、必死で無理を重ね、過労が続いた結果、次の年の秋の始めに、あと少しで一段落というところで、ついに燃え尽きて、うつ状態が再発し、仕事を断続的に休むこととなってしまいました。
うつ状態は、性格的にみて、まじめな、いわゆる執着性格にストレスが加わると、脳内の神経伝達物質が出にくくなり、生きていく活力が失われるもので、症状としては、憂うつ感や不安感などの精神的な症状と、早朝に目が覚めやすくなり、睡眠が十分取れないなどの身体的な症状が見られるのが特徴とされています。軽症とはいえ、早朝に目が覚め、眠れずに良くないことばかり考えて朝を迎えるのを繰り返す日々は、実につらいものでした。もう回復しないんじゃないか、妻や幼い娘たちはどうなるんだと、とても不安な日々を送っていました。加えて、希死念慮という症状があり、死を希望することを念じると書くわけですが、駅のホームに電車が入ってくるとき、吸い込まれてしまいたいと思ったことが何度もあり、できれば思い出したくない、今でも本当に恐ろしい症状でした。
うつ状態の治療は、できる限り静養をして、薬の服用と先生によるミニカウンセリングを受けることが基本となります。カウンセリングでは、自分の症状や仕事の状況などを先生に説明して対応を相談するわけですが、先生やたいへん優しい方で、私にしっかりと向き合って下さいました。しかし、たくさんの患者さんが待っているのに、私のために必ず20分程度も診て下さる先生に、とても申し訳なく思うようになり、2つのことを気づきました。1つは、限られた診療時間の中で、先生に自分の全ての状況をわかっていただいて、適切に問題解決を行っていくには限界があるのではないかということ。もう1つは、うつ状態が再発したため、仮にいったん治ったとしても、執着しやすい自分の性格をどうにかしないと、また再発するに違いないということでした。
手がかりを仏教、真宗に求めて
状態が悪化してすぐ、幸いなことに、職場の上司の判断で仕事量を減らしていただき、それから調子は一進一退を繰り返しました。このため、幼い娘たちを抱えながら私を必死で支えてくれていた妻から、強くすすめられて、思い切って2月の中旬ごろより1月半ほど休職して自宅療養することとしました。その後、ほぼ回復した4月から職場復帰することができました。
こうして回復するまでの約半年の間、どうしていたかというと、仕事を減らしていただいて、膨大な残業や休日出勤がなくなり、少し時間ができたのです。家にいるときは何をする気力もなく、いつもゴロゴロしているような感じでした。そうして、たまたま持っていました手塚治虫さんの『ブッダ』を何度も読み返しているうちに、このような人生の苦悩に向き合っていくには、仏教に何か手がかりがあるのではないかと思い、それからは、仏教の入門書を読みあさるようになりました。
私は学生時代に部活動で柔道をやっていたんですが、OBの大先輩から、柔道は「立禅」、立って行う禅に近い、と聞いたことがあったんですね。それで、冬頃には、近所のお寺の座禅会にも、これだ、とチャレンジしてみました。しかし、座禅会は2時間も座禅を行うもので、活力が回復していなかった私には非常に厳しく、2回通っただけで挫折してしまったわけです。途方に暮れた私は、玉城康四郎先生が書かれたNHKブックス『ブッダの世界』を読み返していました。すると、「念仏でも座禅でも唱題でも、自分に縁の深いことを日々続けていけば、必ず安らぎの境地に到達できる」という一節を目にしました。
その時、そういえば子どもの頃、父の実家で、祖母が仏壇の前で「なんまんだぶつ、なんまんだぶつ」と称えていたなぁと、その姿を思い出したんですね。そうか、もしかしたら真宗の教えなのかもしれない、内容は良く知らないけど、ぜひ真宗の教えを聞いてみたい、と思うようになりました。そして、回復して1月が過ぎた5月の連休中に、インターネットで蓮光寺の「門徒倶楽部」を見つけたんです。
はじめて真宗の教えにふれて 門徒倶楽部で
こうして私は、蓮光寺の門徒倶楽部に参加させていただくようになりました。はじめ、私は仏教・真宗の教えは、安らかな境地に到達するのに、必ず役に立つと思っていました。しかし、座談の場でそのことを話すと、参加しているメンバーの皆さんから「そんなの違う」と、何度もはっきりと言われたのです。
つまり、自分の悩みが解消されて安らかな境地に到達できるというのは、苦悩が取り除けるということ。ところが真宗の教えは、むしろ問題の解決なんかできないんだというところに立てと。そのことを皆さんに何度も教えられ、今思えば、とても貴重なお導きをいただいて、教えの基礎を叩き込んでいただいたと思っています。
いのちのふれあいゼミナール
「門徒倶楽部」にお世話になるのと同時に、当時は副住職だった本多ご住職のすすめで、滋賀県・慶照寺住職の宮戸道雄先生がご講師をしておられた「推進員養成講座・いのちのふれあいゼミナール」にも参加させていただきました。
はじめて聞いたご法話で、宮戸先生は、まず「お寺は習う家」である。何を習うかというと、「自分を習う」ということでした。その日は「王舎城の悲劇」のお話が始まり、この内容は、手塚治虫さんの『ブッダ』のクライマックスにもありましたので、私には親しみやすいものでした。
特に、宮戸先生は、お釈迦さまが韋提希に「汝、凡夫よ」と呼びかけるところを、とても丁寧に繰り返し語られました。そのお声が、私にはとても心に残ったんですね。
また、その日は、今思うと不思議ですが、宮戸先生から、私の課題でもある「我執」について、思うところを書いて下さいと宿題が出たと記憶しております。
帰敬式のこと
その後、「いのちのふれあいゼミナール」への参加がご縁となって、東本願寺の本山研修に参加し、帰敬式を受けさせていただくことになりました。自分なんかが式を受けてもいいのか、と迷いもしましたが、最終的に式を受けようと決心しました。本山研修は、新宿区・専福寺で当時ご住職をされていた二階堂行邦先生がご講師でした。
この時のことについて、当時の記録を少しご紹介したいと思います。
『帰敬式が始まり、剃刀の儀の時に「合掌して下さい」の声で念珠に手を通そうとした。その瞬間、たいへん不思議なことに、なぜかこの念珠を買った時のことを思い出した。この念珠は帰敬式の日から6年半ほど前、結婚後わずか2か月後に妻の母がくも膜下出血で倒れ、その1週間後に亡くなった時に買ったものだった。
帰敬式後、各班に分かれて座談で感想を順番に話すこととなり、門徒倶楽部の法友である、当時31歳の谷口裕さんが、「自分がここに来るまでに31年かかったんだなぁ、と思いました」としみじみ語った。それを聞いて、私も全くそうだと思い、自分も同じように35年間かかりました、と語ろうとした。そのとき、帰敬式の時に思い出した念珠のことから、新婚直後の幸せな日々から一転、母を失って悲しみのどん底に沈んだ妻を支えることができず、どうすることもできなかった自分の無力さや、その後、精いっぱい取り組んだ仕事で行き詰まって、燃えつきてしまい、自分はもうダメなんじゃないかと、絶望的な気持ちで過ごした日々のことなどを思い出し、言葉に詰まって、つい、涙がこぼれ落ちてしまった。「まずい、しっかり話さなくては」と思ったが、なぜか、宮戸先生がゼミナールのご法話の中でおっしゃられていた「汝、凡夫よ」という声を思い出して、何か話そうとしても、「汝、凡夫よ」という声が繰り返し耳の底に響いてきて、本当に涙が止まらなくなってしまい、何もしゃべれないまま、座談の皆さんに「すみません」というのが精一杯だった。そのときの座談のことを思い出してみると、当時のスタッフの方々のご尽力により、しみじみとした雰囲気の中で自分を振り返ることができ、未熟で無力な自分だけども、それでいいのだと、何だか赦されたような、自分で自分を受け入れることができたような、そんな気がしている。』
これが当時の記録として今も大切にしています。この本山研修の時の座談会は、私にとって、当時は恥ずかしさでいっぱいでしたが、かけがえのない感動的な体験となりました。
「凡夫の私」という課題をいただく
その後、本山研修から半年後の夏ごろだったと思いますが、門徒倶楽部で『歎異抄』を拝読しておりますと、後序のところで、『「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、つねにしずみ、つねに流転して、出離の縁あることなき身と知れ」という金言に少しもたがわせおわしまさず』の「金言」の言葉が目に飛び込んできたことを、今でも覚えています。「金言」とは、金のように価値がある言葉といわれます。この、「金言」とされたこの言葉こそ、いのちのふれあいゼミナールなどのご法話で聞いてきた「汝、凡夫よ」ということを、最も的確に表しているものだ、と思ったのです。
さらには、この言葉の前段には、『弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ』とおっしゃられた親鸞聖人のお言葉が記されています。つまり、「そくばくの業」をもち、苦悩に満ちた我が身の事実を深く認識できたときに、如来に頭が下がっていって、南無阿弥陀仏と申していく。そこに救いがあるということで、こうした「罪悪生死の凡夫」という我が身の事実を常に自覚して、お念仏を申す身となっているのか、これが今日に至るまで、私の聞法生活のなかでいつも問われていることです。
いま、感じていること 長崎へのUターン
こうして蓮光寺の門徒倶楽部で聞法させていただき、かつてと変わらない長時間労働にも耐えて、体調管理にも気をつけながら日々を送っておりました。この間、過労で燃えつきたことを教訓に、少しずつ仕事のやり方や職場の人間関係を考慮して働き、国の事務所から受注した仕事で、チームで協力して取りまとめた成果が認められ、思いがけず表彰をいただくなど、精いっぱい取り組んだと思います。
そんな私に、転機が訪れました。2004年3月末に転職のため、長崎にUターンすることとなったのです。Uターンの直前、門徒倶楽部の皆さんに送別会をしていただきました。このとき、だいぶ酔っておられた本多ご住職から「はっし〜、長崎に帰っても、いばらの道で大変だと思うけど、頑張ってくれよ」とのお言葉をいただきました。その時は「いばらの道」と聞いて、「え〜」と思ったことをよく覚えています。しかし今では、その後の私の姿を見抜いた、実に有り難い言葉をいただいたなぁと思っております。
こうして、戻ることはないだろうと思っていた長崎で、思いがけず暮らすこととなりました。転居にあたり、千葉出身の妻や小学校低学年だった娘たちには大きな負担をかけ、今でも本当にすまなかったと思っています。転職してから、私は、主に公共事業の防災工事などに関する現場の監督や様々な調整などの仕事を行っています。長く専業主婦をしていた妻も、今では職を得て仕事に励み、娘たちもおかげさまでどうにか大学生になっています。
長崎での聞法生活
長崎での聞法の場としましては、Uターンしてすぐに、長崎教務所のスタッフや門徒の方々にお世話になり、毎月28日夕方の「ご命日の集い」に10年以上にわたり参加させていただいています。2年前からは、実家がお世話になっている長崎教区1組の照圓寺さんでも、少しずつ聞法させていただくようになりました。
教務所には、1945年8月9日の原爆投下の後、市内に放置されていたご遺体を、当時の説教所長が呼びかけて婦人会をはじめとする門徒の方々が集めて荼毘に付し、その時の約1万5千体から2万体のご遺骨を納めた「非核非戦の碑」があります。原爆で亡くなった方々から、私達のあり方や、真の平和というものが静かに問われています。教務所では、毎月9日に原爆法要を営まれています。この非核非戦の碑を「あなかしこ」で紹介したこともご縁となり、2006年10月中旬には、蓮光寺旅行会で「九州・長崎の旅 ─平和を考える─」として、3日間、蓮光寺のご門徒の皆さんに長崎までお越しいただきました。
長崎教務所での法話会で、本多ご住職より「大切なのは、平和の歩みを続けられない自分のあり方を教えていただくことでしょう。もっと言えば、平和を願いながら戦争をしかねないのが悲しいかな、人間なのです。『さるべき業縁のもよおさば、いかなるふるまいもすべし』という親鸞聖人のお言葉をよくよくいただいていかねばならないと感じました。教えによって、いつも我が身を問い直していく眼をいただき、人間の愚かさ(凡夫)を自覚させていただくことが何よりも大切です」というご法話をいただきました。この時の「平和の歩みを続けられない自分」という言葉は、長崎にいる私にとって強く印象に残っております。
現在、教務所の「ご命日の集い」では、4年ほど前から『宗祖親鸞聖人』の赤い本と、そのサブテキストを少しずつ読み進めています。親鸞聖人の歩んだ道をたどりながら、私たちの生き方、あり方を学ばせていただいています。ご命日の集いでは、6年くらい前からでしょうか、座談会の最後の恩徳讃の前に、金子大栄師が母親にあてたお手紙を拝読するようになりました。このお手紙の一部をご紹介します。
「御慈悲を喜んでお念仏申すのではなく、お念仏の申さるることが御慈悲であります。せつなまぎれの中からもお念仏の申さるるが御慈悲であって、それは母上の御はからいではありませぬ。
凡夫のせつなさに御慈悲が紛れ込んで、お念仏となってくださるのであります。されば、お念仏を申して有難うとなるのではありませぬ。お念仏の申さるることが有り難いのであります。お念仏の申さるること以外に有り難いことがあると思わるるは、はからいであります。」
このお手紙ですが、教務所のトイレに貼ってあったのを、メンバーのどなたかが紹介して座談会の最後に読むようになり、皆さんのお気に入りとなっています。
また、照圓寺では、大内暎信(あきのぶ)ご住職のご法話を聞かせていただいています。大内ご住職は、「正信偈」を題材として本願、信心、念仏、涅槃、浄土などの関係を様々な角度から解説され、お念仏がいかにとんでもない価値のある本当に尊いもので、私たちにとっていかに有り難いかを、繰り返し、口を酸っぱくして力説されています。
ご縁に催された「川に学ぼうかい」の活動
非核非戦の碑がご縁となって取り組んでいる活動を、少しご紹介します。この碑の縁起文には、原爆のあと瀕死の火傷を負った多くの方々が水を求めて亡くなられた浦上川のことが記されています。原爆で数千人もの方が亡くなられたとされる浦上川は、梅雨末期の未曾有の集中豪雨で299名が犠牲となった1982年7月23日の長崎大水害において、この川の流域で80名もの方が亡くなられた川でもあります。
Uターンした直後、私たち家族が暮らすこととなった爆心地に近い近所の浦上川は、ゴミが散乱し、誰も拾う人がいない悲しい状況でした。このため、私は、縁起文に記されたご遺体を集められた門徒の方々に促され、職場の先輩からもすすめられて、はじめ3名で川のゴミ拾いを行い、ボランティア団体「川に学ぼうかいin浦上川(大橋地区)」を立ち上げ、これまで事務局をつとめています。会の名称は、年数回の活動で少しきれいになっても、すぐ雨のたびに多くのごみが流れてきて、いつも川をきれいにするのは限界があるため、少し発想を変えて、川は流域の歴史・文化や人々の暮らしを映し出す鏡といわれていることを考慮し、メンバーで相談して「川に学ぼうかい」と名づけました。愛称は、「川まな」と呼ばれています。
この身近な川の清掃等の活動を通して、防災、環境や歴史・平和などに思いをはせながら、私たちのライフスタイルや自分自身を見つめ直すような場づくりをめざして、「みんなでゆるく細々と楽しみながら」をモットーに、大学生を含むメンバーと2ヶ月に1回の活動を続けてきました。
活動を始めてから、浦上川には、魚類をはじめとするいろんな生きものがいること、江戸時代に信仰を守り抜いた潜伏キリシタンの方々を250年間も支え続けた命の川であったこと、フィールドにある石積み護岸は、戦前、高橋是清が大蔵大臣の頃に全国で行われた時局匡救事業という失業対策事業でつくられ、その後被爆した護岸であることなどもわかってきました。その後、2011年3月の東日本大震災を契機として、過去の災害などの教訓を伝える重要性から、原爆や大水害などの教訓や、川の魅力などを伝える取組みにも力を入れています。ご縁に促された活動で、活動が停滞して自分の力のなさを痛感し、いつまで続くのかと思いながら続けてきました。たまたま、大学に近かったりして、少しずつ輪が広がり、昨年8月には10周年の活動を行うことができました。
川まなの活動ですが、お寺の座談のように、参加者がホッとでき、つながりを感じられる場をめざして、活動の最後に輪になって感想を共有する時間を設けています。先月行った10月の活動を知らせるポスターに、大学生の時から約10年も参加してくれている若手メンバーが記事を寄せてくれました。その中に思いがけず「参加するたびに“多様性を理解し認めあうこと”の尊さを感じる。」という一文を見つけ、とてもうれしく感じた次第です。なお、川まなの活動は、偶数月の第2土曜日の夕方を基本に、終了後は交流会を行っています。実は、みんなで飲みたいという不純な動機も含めて、門徒倶楽部を参考にしています。ちなみに、川まなの活動がご縁で、6年余り前から自治会の役員もつとめています。
無力な私を照らす教え
蓮光寺を訪れて真宗の教えに出遇ってから、もう17年余りになります。私は現在、職場では大規模な工事に関する各種調整の仕事を担当しており、常に起こってくる様々な問題を効果的に解決することが求められています。毎日、知恵を絞り、上司や周囲のメンバーとも相談しながら、何とか日々を送っているのが実情で、スムーズに解決できないことも多く、求められる目標や役割に対して、力不足を感じたり、上司の評価などが気になることもしばしばです。
また、夫婦で共働きとなり、妻の方が私以上に忙しいため、仕事と家事を両立させ、残りの限られた時間で、浦上川や自治会の活動などを、どうにか行っている状況です。仕事が忙しい時に活動の準備が重なったりすると、もう、まさに綱渡りの状況で、イライラしたり、我慢したり、悲しくなったりなどの繰り返しです。
浦上川の活動でも、特に昨年の設立10周年とあわせた被爆70年の記念活動を行うにあたり、浦上川の惨状に向き合うこととなりました。その悲劇と背景を共有し、平和のためにどう取り組むのか、関係する資料や写真・被爆者の方の証言などを掘り起す過程では、余りの悲惨さ・重さ、悲しさ、自分の無力さに何度も涙しました。
こうして、いつも時間に追われて余裕がなく、右往左往し、流転を続けるしかない精一杯の自分、本当に無力で、愚かで、浅はかな自分だと思います。そんな自分でも、真宗の教えは、摂め取って捨てない、阿弥陀さまのおはたらきで、たとえどんな自分でも、決して見捨てない、自分が自分なんだと、自分を引き受けさせていただける、そんな教えではないかと思います。そうしたことがまずあって、「汝、凡夫よ、阿弥陀仏に南無せよ」という呼びかけに、「南無阿弥陀仏」とお念仏を申して、「阿弥陀仏に南無いたします」と応えていく。それが、真宗の基本なんだと思っています。『歎異抄』の「いずれの行もおよびがたき身」である私を照らしてくださる念仏に呼び覚まされて自分の無明の闇が破られていく。自分の力では、とても引き受けられない厳しく、悲しい現実にあっても、お念仏を申すことで、そのままの自分を受け入れていく世界に出遇っていけるのだと思います。そうして、それまでの自分を軸に生きていたあり方から、軸が少しずれることで、ある意味ホッとできるし、「ああ、これでいいんだ。問題解決ができなくても、それでもいいんだ」というところに立てるのでしょう。
教えを聞けば、問題が解決すると思っていたのが、真宗の教えを聞き始めたころまでの自分の思いでした。それが、真宗の教えにふれて、実際に問題解決にはならないけれども、何か問題に向き合う意欲がわいてくるというんでしょうか。自分が生きる原動力に変わっていく、自分の考えとは全く違った、思いもよらない意外な形で救われていくという道があったのです。
ご恩に報いる
祖母は、浦上川の源流部で家族で農業をしておりましたが、原爆から6年ほどして、祖父である夫を原爆症と思われる胃ガンで亡くし、その直後に12人の子どもたちのうち、相次いで幼い3人の娘たちを病で亡くしたと聞いています。その悲しみを抱えて、残された子どもたちを働きながら育てた祖母のお念仏を私は聞いたのでしょう。苦労した祖母は、長生きして97歳まで農業を続け、10年ほど前に99歳で亡くなりましたが、生前「お経はお坊さんがあげるもん、お念仏はうったちが称えるもん」と言っていたそうです。「うったち」は長崎弁で「私たち」ということです。法然上人、親鸞聖人とその後に続いた方々のおかげで、多くの方々を救ったお念仏が、日本の西の端にある長崎の、さらにはずれの「田舎の人々」である祖母を通じて、時代を超えて私に届いたんだ、と思うと、本当に不思議で有り難いことです。「如来大悲の恩徳は 身を粉にして報ずべし 師主知識の恩徳も 骨を砕きても謝すべし」という「恩徳讃」が身に沁みます。
いま、わが国は、少子高齢化・人口減少が進み、財政の危機や格差の拡大、国際社会の緊張などの経済社会のリスクとともに、東日本大震災のあと活動期に入ったとされる地震の発生や、温暖化と気候変動に伴う風水害の激化など、災害のリスクも高まっています。刻々と変化する様々な課題に直面し、平和で持続可能な社会の実現の困難さを実感しています。
私にとって、こうした社会の中にあって、仕事も、家庭生活も、地域のボランティア活動も、全てがご縁によるものです。ご縁にもよおされて、もがき、悩みながら日々を歩んでいく中で、無力で愚かな自分に出遇い、お念仏申すことが、如来の大悲なのであり、私にとって大きな救いで、ご恩、恩徳だと思います。
これからも、このご恩、恩徳に報いるためにも、教えを聞き続け、日々の生活の中でお念仏を申させていただき、自分自身、家族をはじめ縁ある方々、仕事や生活、社会の課題に向き合い、常識を問い直しながら、日々を新たに、身を粉にして精一杯歩もうと思っています。
今日は、まとまりのない、つたないお話ではありましたが、貴重なご縁をいただきまして、本当に有難うございました。
大逮夜法要「法話」 (2)
2017年1月29日公開
法話: 蓮光寺住職(56歳) 「教えの眼から人生を見直す」
苦悩する人間に呼びかける菩提心
橋口さん、どうもありがとうございました。皆さん、いかがでしたか? 非常に苦しみながら、真宗の教えに出遇って、教えを生きるよりどころとして歩んでいる橋口さんの生きざまに様々なことを感じられたと思います。
ただ、橋口さんの苦悩を自分のこととして聞けたかどうか、それがはっきりしないと真宗の学びにはなりません。自分を外したら聞法にはなりませんね。皆さん、どうだったでしょうか。今一度ご確認いただければと思います。
どうにもならない苦悩ということが縁となって、教えを求めるのでしょう。おばあちゃんの念仏の声がよみがえって、橋口さんは真宗に救いを求めたのです。当然、真宗はうつ的状況を治してくれるはずだと、そういうイメージをもってお寺にいらしたのだと思います。ところが、聞法を続けていくうちに、うつ的状況に問題があるのではなく、自分自身のあり方が問題になってくるのです。菩提心、宗教心と言ってもいいですが、人間が立てる菩提心というのは、都合よく解決したいという問題を抱えています。不純といってもいいでしょう。そういう菩提心は成就しないのです。実際、彼が立てた菩提心で彼は救われたのではないのです。それによって彼がうつ的状況を克服して元気になったのではないのですね。苦悩を通して聞法していく中で、橋口さんに呼びかけてくる菩提心(宗教心)に彼が気づかされたという転換がすごいなと思うのです。「汝、凡夫よ」という如来(教え)からの呼びかけ、彼にとってのお念仏といっていいでしょう。その呼びかけによって、自分がうつになるような生き方をしてきたことに目覚められた。自分の思いが自分を苦しめていたのだと。そうすると凡夫の身に帰って、苦悩の中にもう一度戻って、教えに呼びかけられながら生きていこうという意欲を与えられるのですね。そういうことをお話しくださったと思っています。まさに「安心して迷っていこう」という方向性があたえられたのです。
途中で橋口さんは何度も言っていましたが、問題の根っこがはっきりしないと、その仕事の苦しみを逃れられたとしても、また別の苦悩が人間に起こってくる。ですから人生の苦悩を貫くよりどころを持たないと、人間は自分の思いの中に閉塞して、生きたという実感もなく終わっていってしまうのだということを彼から学ばせていただきました。ですから、彼の問題は、皆さん全員が抱えている問題なのです。
人間の価値を有用性でしか見ない社会
人間の存在を経済的価値でしか評価しない社会というのは生きづらいですね。人間が本当に生きる場に社会がなっていないのです。しかし、その社会を作ったものまさしく人間の思いです。自分の思いが社会を作り、作られた社会から、また人間が苦しめられているのです。つまり人間の思いが人間を苦しめているのです。
お年寄りがよく「役に立たなくなった」と愚痴を言われるのは、役に立つのが人間だという価値観を持っているからです。もちろんお年寄りだけの問題ではありません。競争社会の中で、相手を蹴落とさないと生きていけない不安、20時間労働をしないとリストラされる不安、経済的価値で人間の優劣が決められてしまうことに、誰もが不安を抱いているのではないでしょうか。この価値観が、多くの障がい者を殺害した相模原事件の背景にもあるのではないでしょうか。役に立たなければ人間として評価できないという、そういう思いを誰もが多かれ少なかれ持っているのではないでしょうか。現代は、お年寄りから子どもまで孤独、むなしさ、不安に覆われています。人間の価値を有用性だけではかることは、人間の存在根拠を見失わせてしまうのです。
今の社会には人間の思いで作った穢土でしかないのです。橋口君が、この社会のなかに戻って生きていくことができるのは、彼に浄土の環境が与えられたからです。橋口さんの迷いがなくなったわけではありません。ふたたびうつ的症状になることも十分あり得るのです。では依然と何がちがうのか、具体的に言えば、人間の思いを翻して教えの眼から人生を見直す世界が与えられているということです。
関係を自己としてかけがえのないいのちを生きている
もう一点、橋口さんのお話から学ばせていただいたことは、関係を生きるということです。私たちは、親鸞聖人の教えによって、「関係を自己としてかけがえのないいのちを生きている」ことを教えられてきました。ところが有用性のみを価値観としている現代は、便利になった結果、心の通った人間同士のふれあいはなくなりつつあり、代わって機械を相手にして生活することが主流になってしまったのではないでしょうか。そんな状態ですから、まして生まれる前や亡くなった後の関係性など考えるに値しなくなってしまったのではないでしょうか。
ところが橋口さんは、自分より前に生まれたおばあちゃんの念仏を称える声に救われたのです。おばあちゃんのお念仏は、おばあちゃんに伝えた方々がいるわけです。その方々がいなければ、橋口さんはおばあちゃんの念仏の声に出遇うこともなかったのです。そのおばあちゃんの念仏は、親鸞聖人、法然上人にまでつながっているお念仏だったのです。
橋口さんは、自分の存在の背景が見えてきたのです。自分が生まれる前からすでに自分の存在全体を支えるお念仏のなかから自分は生まれたのだと。自分を支えるよりどころをもって生まれたのです。現代はどうでしょう。男女の営みによって子どもができるとしか思っていないのではないでしょうか。存在根拠がはっきりしていないのです。これで不安にならないほうがおかしいですね。孤独とも言えますね。橋口さんは自分が生まれる以前から、自分となってくれるようなお念仏の歴史があった。橋口さんはお念仏の歴史のなかから生まれたのです。ですから、自分が生まれる前の関係性を持っているのです。お念仏の歴史の中から私は生まれたと言える人は絶対孤独ではないですね。そういうなかで、家族に対する感謝の念、利害関係を越えた聞法仲間、ボランティア活動で語り合う仲間、関係性が希薄は現代にあって、橋口さんは本当の関係性を開き続けておられます。橋口さんのおばあちゃんはもう亡くなりましたが、諸仏の一人として「茂、凡夫よ」と呼びかけ続けてくださっています。
「念仏は自我(思い)崩壊の響きであり、自己誕生の産声である」と金子先生はおっしゃいました。過去、現在、未来を貫いて、橋口君は自分の思いを照らし、本当の願いに目覚めよというお念仏の歴史のなかで生かされているのです。
破闇満願(はあんまんがん)
さきほど、現代人は「孤独、不安、むなしさ」を抱えて生きていると申しました。これは人間の思い、自分を絶対化して疑わないことがもたらした結果なのでしょう。人間の思いは構造的に「孤独、不安、むなしさ」という問題を抱えているように感じました。
人生を旅に譬えると、現代人は旅先のことばかり考えているようなものです。旅先で楽しいかつまらないか、損か得か、そんなことばかり考えているのではないでしょうか。しかし、旅全体を支えているのは帰る家があるということなのです。ただ帰る家ではなく、自分の在り方に厳しく呼びかけながら包んでくれるような家です。それを「浄土」と言うのでしょう。本願が南無阿弥陀仏となって呼びかける世界が「浄土」です。念仏は、どんな自分もかけがえのない存在として受け入れて生きていける者になってほしいと呼びかけ続けています。私たちは如来に願われている存在なのです。
曇鸞大師が、仏教は「破闇満願」(はあんまんがん)の教えだと言われました。つまり自分の迷いの闇が破れて本当の願いに立っていく。願いが満たされる。本願ですね。本当の願い。そのままで尊いということにうなずけるというのが、私たちの一番の課題なのでしょう。
橋口さん、本当にありがたくお話を聞かせていただきました。教えの眼から人生を見直された橋口さんの歩みに頭が下がりました。わざわざ長崎からご来寺くださいまして心より御礼申し上げます。
報恩講の夕べ
2017年3月21日公開
トーク&コンサート:鈴木君代さん(真宗大谷派僧侶、シンガーソングライター)
いつも健康的でパワフルな鈴木君代さん。しかし、今回はかなり心身共々疲れているようでした。かなり痩せてしまって、ご門徒からもずいぶん心配の声があがりました。
人間、生きている以上、どうにもならないことにも出くわしていかなければなりません。自分が大切にしていた友人が亡くなったり、立ち直れなくなるほどひどいことを言われたり、ご自分が抱えている問題を少し吐露しながらも、そんな自分をいつも南無阿弥陀仏が寄り添ってくださっていることへの感謝についても語られました。
苦しいときは恩師の和田稠先生を思い出すそうです。君代さんは、大谷祖廟に勤務していた時が一番自分にとって勉強になったと言います。そ「大谷祖廟に来られるすべての人を如来聖人の大切なお客人として、お待ち受けすることがあなたの大事な御用なのですよ」と和田先生から言われたことが身に沁みていて、様々な気持ちを抱いてお参りに来られる人から多くのことを学んだと言われました。人間は関係の中で育ち、関係の中で苦しむのですが、それがすべて南無阿弥陀仏からの励ましだと言われました。
曲目
- 恩徳讃
- いのちの花を咲かせよう
- 白骨の御文
- 兵戈無用
- ふるさと
- お坊さんにあこがれてお寺にはいったの
- ブラジル(アンコール)
晨朝法要
2017年3月21日公開
勤行と感話
3日(火)朝8時より晨朝法要が厳修されました。東本願寺で帰敬式を受けた法友を代表して、昨日法話された橋口茂さんと谷口裕さんが感話をされました。晨朝法要に参詣したご門徒のうち、彼らと本山でいっしょに帰敬式を受けた篠崎一朗さんや日野宮久夫さんもおられ、とても感慨深く2人の感話を聞かれていました。
橋口さんが涙したことに谷口さんたちは泣くものかとぐっとこらえていたようです。皆それぞれの苦悩があって、親鸞聖人の教えに出遇われました。お二人の感話はその喜びにあふれていて、参詣者もみな共感されていました。
晨朝法要は30名ほどの参詣ですが、とてもアットホームです。朝の静けさの中での勤行、そして感話を聞くと、何かとても満たされた気持ちになります。
満堂の大逮夜法要や日中法要はもちろんいいですが、朝の静けさのなかでの晨朝法要には一味違った厳粛さがあります。ぜひ一度、晨朝法要に御参詣ください。
日中法要(御満座)「法話」
2017年3月3日公開
法話: 狐野秀存先生(京都大谷専修学院長、68歳) 「念仏往生とふかく信じて」
日中法要


草間総代の挨拶

櫻橋淳さん感話

狐野秀存先生

法話の様子


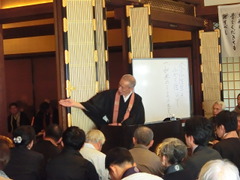
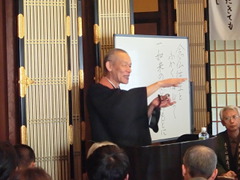

俱会一処(くえいっしょ)
この身はいまはとしきわまりてそうらえば、さだめてさきだちて往生しそうらわんずれば、浄土にてかならずかならずまちまいらせそうろうべし。
これは、ご開山親鸞聖人の、晩年の手紙の一節でございます。親鸞聖人のお手紙を集めた『末燈鈔』の第十二通に載っています。
残念ながら、日付が書いていないものですから、いつお書きになったのかは定めることはできませんけれども、内容からすれば相当お年を召されたときのものであろうと思われます。
お年を召された親鸞聖人は、「きっと皆さん方よりも先だって浄土へ往生することになると思います。浄土で必ず必ず皆さんをお待ちいたしましょう」とおっしゃっています。どんな人もこの今生の苦労多きいのちを終えれば、浄土への往生を果たし遂げて、そして仏のさとり、お釈迦さまと同じようにほとけのさとりをいただく。そういう尊いいのちを、唯一無二の何ものにも代えがたい尊い人生をいただいているのでございます。そういうことをお述べになっておられます。
今の親鸞聖人のお手紙の言葉に、「念仏往生とふかく信じて、しかも名号をとなえんずるは、うたがいなき報土の往生にてあるべくそうろう」というはし書きがあるものですから、このたびは「念仏往生とふかく信じて」という題を出させていただいたようなことであります。
最初に、如来のもとにということで、私どもは誰もみな、阿弥陀如来の「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」のこころに照らされているのですね。竹中智秀先生はその如来の摂取不捨の心を、「えらばず、きらわず、見すてず」と教えてくださいました。その如来の心のもとに、その心の光に照らされているのだということを、昨年私自身の身の上に起こったことを通して、お話ししたいと思っております。
皆さま方のお手元に、「俱会一処(くえいっしよ)」と題する紙が配られているかと思います。『大法輪』という宗教雑誌がございますが、昨年の12月号に寄稿させていただいたものです。
俱会一処
寺の建ち並んでいる寺町を歩いていると、境内の墓地の墓石に、「何々家先祖代々」や「何々家累代」と刻んだ場合が多いが、墓の正面に「南無阿弥陀仏」または「俱会一処」と書いてあれば、そこは浄土真宗の寺だとわかる。
「俱会一処」は浄土の徳をあらわす。『阿弥陀経(小経)』に念仏往生を勧める釈尊の言葉として説かれる。
舎利弗(しゃりほつ)よ、この娑婆世界の苦を受けている者は、阿弥陀仏の極楽世界のすばらしいはたらきを聞いて、発願(ほつがん)してその阿弥陀仏の国へ生まれたいと願うべきだ。なぜかというと、阿弥陀仏の国は無量無数のよき師、よき友が待って迎え、みな共になかよく集まり一つになって出会うことができるからだ。
この世の悲しみの一つに愛別離苦がある。どんなに愛しい者であっても、いつかは別れなければならない。いのちある者の定めである。その別れに身もだえするのは煩悩だということは十分わかっていても、それでもつらく悲しい。
いのちの行方(ゆくえ)を問わずにいられない煩悩具足の凡夫のために、釈尊は阿弥陀の本願を説き、念仏往生の道を勧めた。「俱(とも)に一処に会(え)する」。本願を信じ、念仏を申す中で、必ず浄土で再会すると示した。別れの悲しさを内にやさしくつつみ、顔を上げて今生(こんじょう)のいのちを生きる姿勢を教えられたのである。
ひとりで死んでいく寂しさ
昨年書いたものですが、自分でもこういう文章はもう二度と書けないだろうなと思っております。
昨年の夏の終わり、8月の末に郷里のすぐ上の兄から電話がかかってまいりました。「2番目の兄がこの夏の間に入院して、お医者さまからは、長くてあと3ケ月であろうと言われているんだ。おまえも長い間帰ってきていないから、一度帰ってこい」という電話でした。
私は、石川県の金沢の生まれです。それは大変だということで、早速兄の見舞いに金沢へ帰ったわけです。受付で教えられた病室に行きますと、4人部屋にその2番目の兄がおりました。ちょうど窓際のベッドでした。病室の入り口で、「しんちゃん」と声をかけました。しんちゃんというのは、2番目の兄の名前です。正しくは心念(しんねん)という名前です。誰が聞いても、それでお寺の子だなということが一発でわかるような名前です。
「しんちゃん」と声をかけましたら、それまで窓の景色を眺めていた兄が入り口の方に寝返りを打ったわけです。私の顔を見た途端、うおお〜と号泣、泣き出したのです。慌てて兄のベッドのそばにかけよって、本当に赤子のように泣きじゃくっている兄の背中を撫でさすりながら、「しんちゃん、みんないっしょにいるから」ということを、くり返し語るしかありませんでした。
肩を震わせながら泣いている兄の背を撫でさすりながら、震える兄の背中から私の手のひらに伝わってくるのは、「寂しい」ということでした。兄にはお医者さまの所見は伝えていないのですが、やっぱり本人が一番よくわかるわけです。長くないなということが。
一人死んでいかねばならない寂しさですね。死ぬときはどんな人も、たとえ親でも兄弟でも、人生の苦労を共にした夫婦であろうとも、いっしょに死んでいくわけにはいかないのです。一人ひとり、自分の死を迎えねばならないのです。そういうどうしようもない寂しさというものが、泣きじゃくる兄の背を撫でさすりながら伝わってくる思いがいたしました。
兄は久しぶりに弟の顔を見て、こらえていた寂しさが一気に吹き出してきて、赤子のように泣くというかたちになったのだろうと思います。「早く元気になってね」とか、「大丈夫」とか、そういうおためごかしのようなことは、もう言える段階ではありませんから、ただ、「みんなしんちゃんといっしょにいるんだ」ということを、くり返しくり返し言うしかなかったわけであります。
しばらくすると、兄も感情がおさまってきたのでしょうか。「実は、体のあちこちが痛くてかなわないんだ」と。肺がんだったのですが、少し転移が始まっていました。「痛い痛い」と言いながらも、久しぶりに会った弟なものですから、お互い小さいころの思い出話をするわけです。
2番目の兄と私は7つ違いなのですが、自坊の背戸に柿の木がありまして、私がまだ学校に上がる前のころだろうと思います。ちょうど今頃の季節ですね、小学校の高学年だった兄がその柿の木に登って、柿をもいで、下で待ち受けているまだ小さい私に、ほいほいと投げてよこすということがあったのです。ところが、どうしたはずみか、足を掛けていた枝がぽきっと折れてしまいまして、そこから兄が真っ逆さまに転げ落ちてしまったのです。結構高かったですね。2、3メートルもあったでしょうか。幸い大きなけがはなかったのですが、大変な事が起こったわけです。兄は「おまえのためにえらい目に遭った」と言っておりました。
それから、大きくなって、私が東京の大学に進んだときに、下宿代がもったいないものですから、まだ独身だった兄のアパートに転がり込んだのです。田舎の親には下宿しているというふうにして、下宿代だけはしっかり送ってもらいながら、実は兄のところに転がり込んで、それを浮かして自分の小遣いにしようというようなさもしい魂胆でした。ただで寝泊まりさせてもらうわけにはいきませんから、私がおさんどん(台所仕事)をしていたのです。だけど、18や19歳のおさんどんですから、たかが知れているわけです。だいたいつくるのはカレーライス。この時期になるとおでん。あれは具さえ変えておけば1週間ぐらい持つわけです。兄が会社の勤めを終えて帰ってくると、また今日もおでんかというようなていたらくだったのですが、1週間以上もカレーとおでんを食わされたという笑い話をしておりました。
「また見舞いに来るから」ということで病院を出て京都へ帰ったわけですが、学校が始まりますと、やはり何かと忙しくて、気にはかけていたのですが日にちが過ぎていきました。
兄の危篤で胸の中に浮かび上がってきた「俱会一処」という言葉
そうこうするうちに、ひと月半ほどたった10月の上旬でした。実はもう8月の始めに、先ほど読んだ『大法輪』という雑誌から、年末の号で日本の仏教の各宗派の特集をするけれども、天台宗なり、真言宗なり、禅宗なり、日蓮宗なり、それぞれの宗派の方たちに大切にしている言葉を抜き出してもらって、それについて簡単な解説を書いてほしいと。ついては、浄土真宗の教えの中で一番大切な言葉を一つ書いてほしいと。各宗の方がそれぞれ書かれるということなので、「わかりました」と引き受けたわけです。
いつも、引き受けてからあとで困ってしまうのですが、いざとなると何も浮かばないわけです。それも気にかかりながらずるずると先延ばしにしておりまして、いよいよ締め切り日が来たわけです。何が何でも今日中に書かなければいけないということで、学校が終わりましてから家に帰って、机の前に真っ白の原稿用紙を広げて、腕組みをしながら、これぞ浄土真宗という言葉、何だろうということで、思案投げ首で考えているうちにどんどん時間が過ぎていきました。
夜の10時近くになったころかと思います。そこへ再びすぐ上の兄から電話がかかってきまして、夏に入院した2番目の兄が危篤だと。今晩、あすというふうにお医者さんは言っているので、すぐ来いという電話でした。「わかった」と返事はしたものの、困ってしまったのです。一方で約束の原稿があるものですから、「わかった、すぐ帰るけれども、今どうしても仕上げなければならないことがあるので、それを仕上げたらすぐ帰るから、もうちょっとだけ待ってほしい」と返事をしました。
あれほど困ったこともめったにありません。どうしようかと。一方で、兄の危篤の知らせを聞いて、もう一方で、何か書かないといけないという。そのときに、理屈も何もないですね。ふっと私の胸の中に浮かび上がってきたのが、この「俱会一処」という『阿弥陀経』の言葉でした。
果たして、この言葉が浄土真宗の教えを代表する言葉であるかどうかはわかりません。しかしながら、そのときの私にとってはこの言葉しかない。「俱会一処」。これが浄土真宗のすべてだという思いがありました。
ともにいっしょに会する。みんなともに一つの処に出会うという「俱会一処」という言葉がふっと胸に浮かび上がってきましたら、あとの文章はどういうふうにして書いたのか覚えていません。「俱会一処」というお経の言葉に導かれるように、筆が、手が自然と動いたという感じです。
書き上げまして、それから支度を調えて、京都から金沢へ向かいました。病院に着いたのはまだ夜が明ける前でしたけれども、兄の病室に入りましたら、酸素マスクをして、肩ではあはあ息をしながら、もう全身に病巣が転移しているのでしょうか。エビのように体を折り曲げるようにして、苦しんでいました。「しんちゃん、しんどいな。えらいな」という言葉しかかけられなかったわけですけれども。
折りの悪いことに、その日も、どうしても京都でしておかなければならない仕事があったものですから、親類の人に訳を言って、京都の仕事を終えたらまたすぐ戻るからということで、とんぼ返りで京都に戻りまして、済ませなければならないことを済ませて、再び金沢に向かいました。もう日付が変わっておりました。
病室に行きましたら、兄の息子、甥っ子が1人おりまして、「おじちゃん、先ほどお父さん、楽になったんだわ」と言いました。お身内でそういう看取りをされた方は、みなご経験があると思うのですが、末期がんの痛みというのは耐えられないそうです。
前日、少しだけ兄を見舞ったときも、お医者さまから、私と電話をかけてきたすぐ上の兄と、そして甥っ子の3人が呼ばれまして、「どうされますか」と声をかけられたのです。
どうされますかというのは、末期なものですから体中が痛みで耐えられない。その痛みを和らげるために緩和治療をする、いわゆるモルヒネを投与するのです。一時は痛みが和らぐのですが、そんなに長く続くわけではない。しかも、それがだんだん効かなくなってくる。そうすると、モルヒネの量をさらに増やすということになっていくわけです。
モルヒネを投与すると、そのときはしばらく痛みが和らぐのですが、それは同時に、死期を早めてしまう。直接的には心臓に非常に大きい負担をかけるわけです。お医者さまは綱渡りのようなかたちで、何とか病人の痛みを和らげてということなのですが、もう、いよいよぎりぎりのところに来て、これ以上モルヒネの量を増やせばいのちに関わるという段階になると、お医者さまも困ってしまうわけです。
それで私ども身内に、「どうされますか」と聞かれたわけです。本来は本人に聞くべきなのでしょうけれども、本人は痛みで七転八倒の苦しみですから、私たち身内に聞かれたわけです。3人、期せずして、「何とか痛みを和らげていただきたい。あとはお任せします」としか言えませんでした。そういう最後の苦しみを見ているものですから、「お父さん、やっと楽になったよ」と言う甥っ子の言葉通りだったのですね。
生理的な反応でしょうけれども、息を引き取ると筋肉の緊張が解かれるわけです。昨日、あれほど眉間にしわを寄せて苦悶の表情でいっぱいだった兄が穏やかな顔で寝ているものですから、私もやっぱり、「しんちゃん、ご苦労さんだったな」と声をかけました。
真宗の葬儀 生まれてきた阿弥陀さんのもとに帰っていく
その兄は長男ではなく2番目ですから、お寺を出て自分で小さな会社をやっていたのですけれども、やはり寺で生まれたものですから、お寺で最後を見送ろうということで、寺に兄の遺体を移しました。
お寺の葬式というのは非常に簡素なものです。お寺の場合は、親戚から若干の花が届きますけれども、本来は野卓(のじょく)といいまして、何もないのです。ご本尊の前にお棺を安置して、野卓を置くだけです。
今日は蓮光寺さまの報恩講ですので、前卓の上に、鶴亀(つるかめ)の燭台2つと花瓶(かひん)2つ、そして真ん中に香炉という、5つのものがございますが、これを「五具足(ごぐそく)」と申します。普段は鶴亀の燭台と花瓶、香炉の「三具足(みつぐそく)」です。
お寺の葬儀の場合、三具足の野卓を置くだけです。ただし、普段と違うところは、花瓶に紙花というものを立てるのです。
よくあるのは、細い竹棒などに切れ込みを入れまして、そこにお宮さんに行くと御幣というのですか、ひらひらとした紙のようなものがありますね。あのように紙を細長く切りまして、それを芯の棒に差し込んでいく。そういうものを立てるのです。何でも、お釈迦さまがお亡くなりになったときに、四隅に沙羅(シャラ)の木が2本ずつありまして、ですから沙羅双樹というのです。その沙羅の木の花びらが、自然の草花もお釈迦さまの死を悼んで、はらはらと散ったという故事があります。それになぞって、そういう紙花(しか)というものを立てるのだと言われていますけれども、詳しいいわれはよくわかりません。
お飾りはそれだけです。あとは、時に根菓餅(こんかべい)といいまして、自然のものを供えることもありますけれども、まったくあっさりしたものであります。そういうお寺のお葬式という形で、いよいよ出棺ということになりました。
葬儀社の方がお棺の片方のふたを開けて、亡くなった方の顔が見えるように、今はなっておりますね。そういうかたちでふたを開けられて、いよいよ出棺でございますので、皆さまお別れをどうぞということで、親族と兄の別れになるわけです。
私も兄の亡きがらの顔を見ながら、「しんちゃん、いよいよこのお寺ともお別れなんだ」と。「これからこのお寺を出て行くよ」と、こころの中で声をかけました。そして、葬儀社の方が「よろしゅうございますか」ということで、ふたを閉められます。
ちょうどこの蓮光寺さまと同じように、皆さんの後ろ正面ですね。そこを向拝(ごはい)と申すのですが、階段状になっております。葬儀社の方がお棺を持って階段を下りて行かれる。ただし、私の金沢の寺は、何十年か前に区画整理にあったものですから、階段を下りたすぐ下が今は道路になってしまって、そこに寝台車が待っていました。
今でも不思議な気持ちなのです。なぜそういうことをしたのかわかりませんけれども、寺の本堂を出て行く兄のお棺を見送りながら、何気なくふと後ろを振り返ったのです。お寺の本堂ですから、真ん中にご本尊の阿弥陀如来像があります。それが目に入りました。その時、ああ、そういうことだったのかと。それまで、もやもやと霧のように私のこころを覆っていたものが晴れていく気がいたしました。
というのも、先ほど申しましたように、夏の終わりに病院へ兄を見舞いに行って、全身を震わせるように泣きじゃくっている兄の背を撫でさすりながら、みんな一緒にいるからと言いながらも、その寂しさを体全体で訴えている兄と、どうしようもない断絶と申しますか、何か深く離れた感覚ですね。
兄弟とはいえ、今一人死にゆく寂しさに泣いている兄に、どうすることもできない。ただ黙って見ているしかない。いったい兄、弟と言いながら、本当にどこで出会ってきたのかということが、何か釈然としない思いというものが、ずっと私の胸に張り付いていたわけです。
最後亡くなって安らかになった兄の顔を見たときも、「しんちゃん、楽になったね。大変だったね」と声をかけながらも、結局出会うことなく兄は一人亡くなってしまったんだなという、何か自分の気持ちの中に溶けない塊のようなものをずっと抱えていたわけです。
それが、出棺ということで寺を出て行く兄を見送りながら、「しんちゃん、いよいよお別れだね」と言いながら、何気なくふと振り返ったときに阿弥陀さんの姿が目に入った。その時に、ずっと抱えていたわだかまり、何か得体のしれないの塊のようなものがすっと溶けていって、そういうことだったのかと。
そもそもの初めから、この阿弥陀さんのもとにいたんだなと。そういうことが理屈抜きに胸の中にひろがって、こころの落ち着き処を見いだしたわけです。
今、こうしてお棺に入って出ていこうとしている兄も、この寺の、この阿弥陀さんのもとで、「おぎゃあ」と今生のいのちを受けた。それから何年かして、また私も弟として、この阿弥陀さんのもとで、「おぎゃあ」といのちを受けたのだと。
そして、兄弟として、兄は柿の木から落っこちたり、私に1週間、カレーとおでんばかり食わされながら、そういういろいろなことがありながら、大きくなってからは、年に一度、盆暮れに会うかどうかということしかないわけですけれども、会えばやっぱり、兄弟ですから、特別何の話をするわけでもありません。男の兄弟というのは、だいたい、「おお、元気か」と言うだけで終わるようなものですけれども、それでも、黙っていても気持ちが通じ合うようなところがあります。
そういうかたちで、兄として、弟として過ごしてきて、今兄は今生のいのちを終えてこの寺から出て行くわけだけれども、それはもともと生まれてきた阿弥陀さんのもとに帰って行く。
より正確に言えば、阿弥陀如来の「摂取不捨」の心の光の世界に帰って行くのだなと。今、それを見送っている私も、おそらく何年か後には、同じく阿弥陀さんの心の中からこの世に生まれてきたのならば、またそこに帰って行くのだろうなと。
そもそもの始まりから、そして今生のいのちを尽くしたその永遠の未来に至るまで、如来の心の中に初めからいたのだなという、そういうことが無条件に、理屈抜きに私のこころの内に落ち着き処を見いだしてきたようなことです。
念仏往生の道
あらためて、最初に申しました、親鸞聖人のお手紙の一節を憶い起こしました。「この身はいまはとしきわまりてそうらえば、さだめてさきだちて往生しそうらわんずれば、浄土にてかならずかならずまちまいらせそうろうべし」という、この親鸞聖人の言葉が、本当にありがたい言葉だなと。私どものこの今生の娑婆の人生で、いろいろな姿かたちがあるわけですけれども、皆共に一つに必ず出会うことのできる、そういう如来の本願の心というものを示してくださったのだなと思いました。
若いころは生意気ですから、この親鸞聖人のお言葉も何度か読んでいたのですが、浄土で待っているとか言われると、親鸞聖人も年をとって、ちょっと気弱になられたのかなという程度にしか思っていませんでした。本当にご無礼なことです。
「浄土にてかならずかならずまちまいらせそうろうべし」と、「かならずかならず」という言葉を2度繰り返して、おっしゃっておられます。私どもがこの今生の、今こうしていのちをいただいて生きているこのいのちそのものが、実は念仏往生の道を歩く今の「ひとときのいのち」だということを念をおして教えていらっしゃいます。兄の死をきっかけに、このことをあらためて教えられたことであります。
それで、今日もう一枚、皆さま方のお手元に信國淳先生の書かれた言葉を配らせていただきました。これを最後に皆さまと一緒にお読みして終わりたいと思います。
この言葉を書かれた信國先生の写真を持ってまいりました。写真が小さいので見にくいかもしれませんけれども、黒板の右側にいらっしゃるのが信國淳先生です。先生は、1980年2月にお亡くなりになったのですが、その前年に、新潟県長岡市に行かれたときの写真です。お元気なころの最後のお姿だと思います。このあと先生は病気になられて、そして翌年お亡くなりになりましたから、非常に懐かしい写真です。黒板の横でふんぞり返っているようなお姿ですが、これは別に威張っていらっしゃるのではないのです。実は少々、腹立ちのポーズなのです。というのは、黒板にチョークでたくさん字が書いてありますように、2日間にわたって、どんな人も皆、同じ一つの尊い阿弥陀のいのちを生きているんだということを、熱心に講義をされたのですが、それを聞いている私どもがぼんやりしているものですから、とうとう2日目に先生の堪忍袋の緒が切れて、「君たちはどうしてこんな簡単なことがわからないのかね」と言って、ちょっと立腹なさっているのです。そういう意味でも非常に懐かしい写真です。
このときにお話をされたことを簡潔に述べているのが、今、皆さま方のお手元にお配りした信國先生の言葉です。これをご一緒に読んで終わりたいと思っております。よろしいでしょうか。
我ら皆共に安んじていのちに立たむ いのち即ち念仏往生の道なればなり 淳
私どもは皆、実は如来の光に照らされた無上のいのちを与えられて生きているのだと。そういうことを教えていらっしゃる言葉だと思います。
ようこそお参りいただきました。
御礼言上
2017年3月3日公開
司会の上野ちひろさん

御礼言上 御礼を申し上げているのは河村和也総代


お斎の様子(手作り精進料理です)



2016年の報恩講が昨日、本日の一昼夜にわたり厳修されましたことは、私ども蓮光寺門徒一同、大きな喜びとするところでございます。如来のご尊前、宗祖のご縁前にご満座の結願致しましたことを報告するにあたり、ご出仕、ご出向くださいました皆さまに、一言お礼を申し上げます。
ご法中の皆さまにおかれましては、ご多用のところご出仕くださり、ねんごろなるお勤めをたまわり、誠にありがとうございました。つたないながらお勤めをご一緒させていただき、当派に伝わる称名の伝統を、この身をもって感じたことでございます。
昨日のお逮夜では、蓮光寺の門徒である橋口さんと、当山住職の法話を伺いました。橋口さんからは、苦悩のうちに教えに出遇った喜びが語られ、住職からは、苦悩を生み出す人間のありようが問いただされ、私どもの聞法の歩みを振り返る機縁をいただいたことでございます。
また、それに続く報恩講の夕べでは、鈴木君代さんのお話とお歌を拝聴し、君代さんの生きざまと強いメッセージにこころを動かされるとともに、お聖教の言葉が新たな旋律を得る瞬間に立ち会った思いがしたことでございます。
本日、晨朝のお勤めでは、普段法座を共にする二人の感話を聞き、一人ひとりの身に、その人にしか歩むことのできない聞法の歩みのあることを、あらためて実感致しました。
また、日中の法要では、蓮光寺門徒の櫻橋さんの感話を伺い、深い信仰の故の絶望と、その絶望の内に阿弥陀仏の教えに出遇われたことの不思議に引き込まれる思いがしたことでございます。
さらに、狐野先生には京都よりご出向いただき、ご法話を頂戴致しました。お浄土に帰られたお兄さまのご出棺に際し、如来の「摂取不捨」のこころの光の内に人間の存在のあることを感じ取られたとのお話は、ああ、そうだったのか。そういうことだったのかという言葉とともに、こころの奥に深く響いたことでございます。
今年の報恩講に貫かれていたものは、一人ひとりが教えに出遇うに至る歩みと、教えに生きる歩みを語り開き、確かめ合うことであったかと振り返っております。教えは人に気づき、人を通じて、この私の身にまで伝わってまいりました。そのありがたさをいまさらのように感じたことでございます。
この寺が、この先も南無阿弥陀仏の教えを伝え合う場としてあり続けるために、住職、坊守を先頭に、門徒一同、聞法に精進して参りたく存じます。どうぞ、ご出仕、ご出向の皆さま方には、変わらぬご指導とご鞭撻を賜りたく、伏してお願い申し上げる次第でございます。
2016年の蓮光寺報恩講のご満座結願にあたり、重ねてお礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。このたびは誠にありがとうございました。